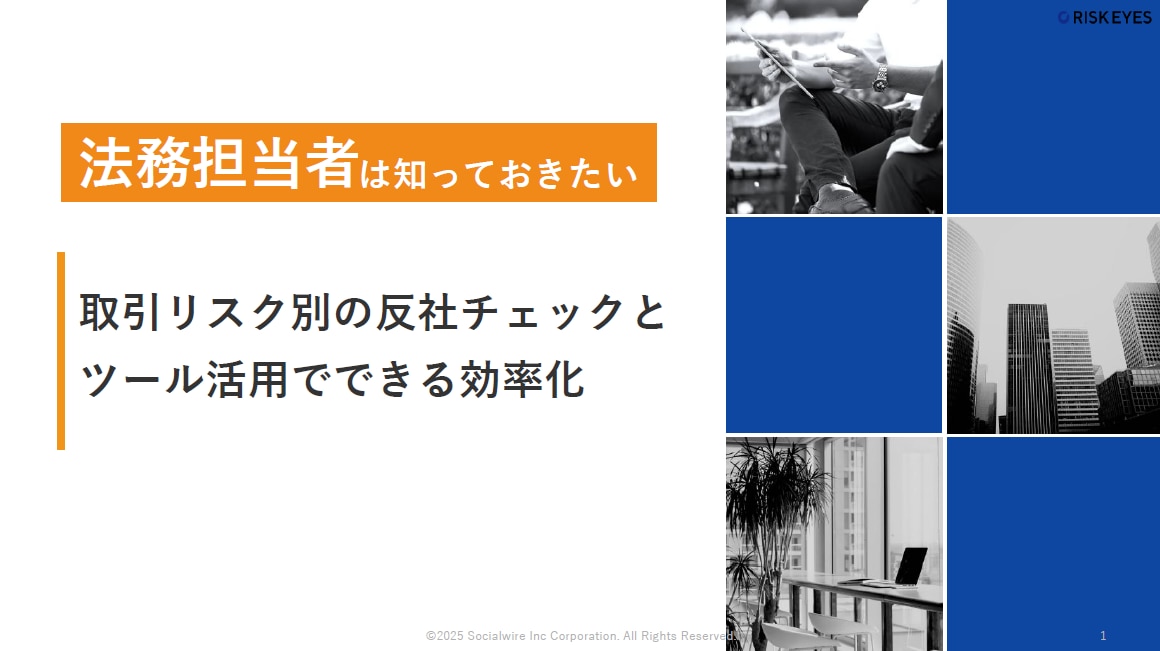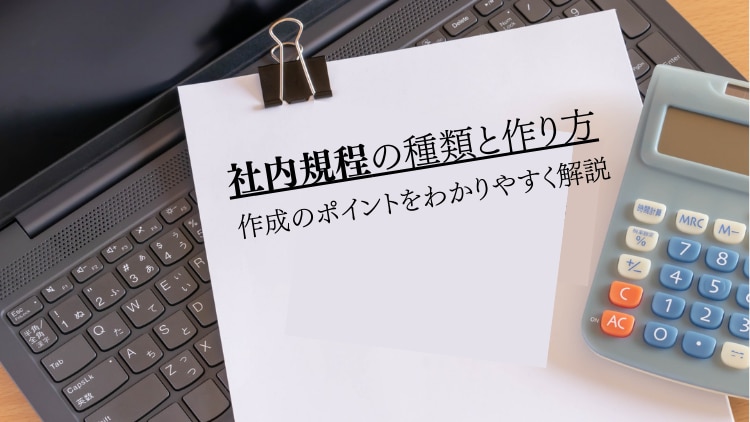
社内規程の種類と作り方、作成のポイントをわかりやすく解説
社内規程は、企業運営を円滑に進めるための重要なルールです。
適切な規程を整備することで、業務効率化やトラブル防止、従業員の働きやすさ向上が期待できます。
この記事では、社内規程の種類や具体的な作り方、作成時のポイントをわかりやすく解説します。
初めて規程を作成する方や、見直しを検討している方に役立つ情報をお届けします。
企業の成長を支える基盤として、社内規程の重要性を再確認しましょう。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】取引リスク別反社チェック効率化の方法
目次[非表示]
- 1.そもそも社内規程とは
- 1.1.社内規程を作成する目的
- 1.2.就業規則との違い
- 2.社内規程の種類
- 2.1.定款や企業理念など基本経営・会社の運営に関する規定
- 2.2.組織図や職務権限規程などの組織権限に関する規定
- 2.3.就業規則や給与に関する人事労務規定
- 2.4.安全衛生管理や文書の取り扱いなど総務関連の規程
- 2.5.経理規程や在庫管理規程等の業務管理
- 2.6.その他の社内規程
- 3.社内規程の作り方
- 3.1.①現状分析と目的の明確化
- 3.2.②情報の収集
- 3.3.③草案の作成
- 3.4.④社内での検討と意見聴取
- 3.5.⑤専門家によるレビュー
- 3.6.⑥最終調整と承認
- 3.7.⑦従業員への周知と説明
- 3.8.⑧運用と見直し
- 4.社内規程を作成する際のポイント
- 4.1.作成する優先順位を考慮する
- 4.2.法律に抵触しないようにする
- 4.3.監督官庁へ必要な届出を行う
- 4.4.従業員への周知を徹底する
- 4.5.定期的に見直しを行い、内容を更新する
- 5.社内規程に法的拘束力はある?
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの効率化を学ぶ】
そもそも社内規程とは
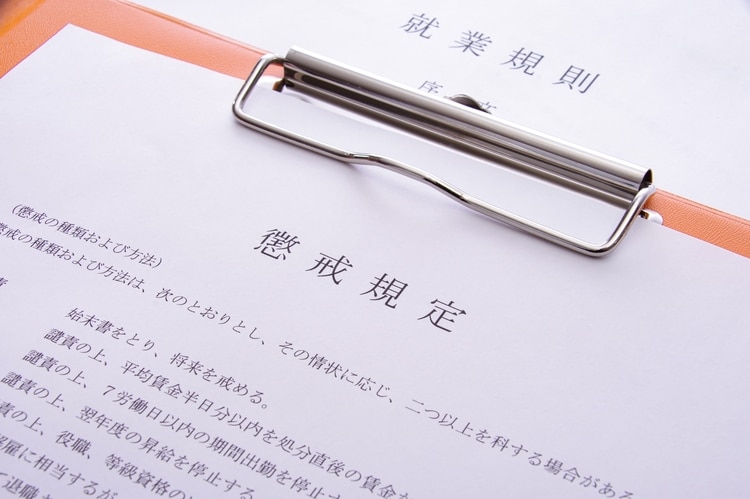
社内規程とは、企業内でのルールや基準を定めた文書のことです。
これにより、業務の効率化やトラブルの防止、従業員間の公平性の確保につながります。
社内規程は、企業の規模や業種に応じて内容が異なりますが、共通して企業の運営を円滑にするための重要な役割を果たします。
社内規程を作成する目的
社内規程を作成する主な目的は、企業内での統一されたルールを確立し、従業員が安心して働ける環境を提供することです。
社内規程があることで、業務の透明性が向上し、従業員間のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、企業の成長に伴い、業務が複雑化する中で、明確な規程があることで効率的な運営が可能となります。
さらに、社内規程は企業文化を反映し、従業員に企業の価値観や目標を共有する手段としても機能します。
就業規則との違い
社内規程と就業規則は混同されがちですが、明確な違いがあります。
就業規則は労働基準法に基づき、従業員10名以上の企業に作成が義務付けられたもので、労働条件や賃金、労働時間などを定めた法的拘束力を持つ文書です。
一方、社内規程は企業独自のルールを定めるもので、法的拘束力がない場合もあります。
例えば、服装規定やテレワーク規定など、企業の文化や働き方に合わせた内容を自由に設定できます。
関連記事:IPO準備時に必要な社内規程(社内規定)の整備とは 作成の注意点を具体的に解説
社内規程の種類
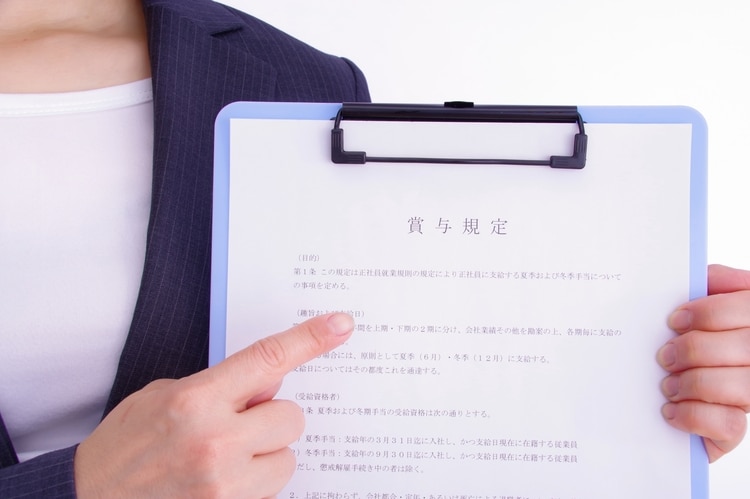
社内規程は、企業の運営を円滑に進めるために必要なルールや基準を定めた文書です。
これらは企業の規模や業種に応じて異なりますが、主に以下の6種類に分けることができます。
定款や企業理念など基本経営・会社の運営に関する規定
企業の目的や理念を明確にするための規定です。
定款は会社の基本的な運営方針を定め、企業理念は従業員に会社の価値観や目標を共有する役割を果たします。
これらは企業の方向性を示し、従業員が一体となって目標に向かうための基盤となります。
- 定款:会社の目的、役員の人数、営業年度などを定める。
- 企業理念:会社の価値観や目標を明文化。
- 取締役会規程:取締役会の決議事項や報告事項を規定。
- 株式取扱規程:株式の発行や管理方法を定める。
関連記事:経営戦略とは?目的と段階を解説 知っておくべきキーワードも紹介
組織図や職務権限規程などの組織権限に関する規定
組織の構造や役割分担を明確にする規定です。
組織図は各部署や役職の関係性を示し、職務権限規程は各役職の責任範囲や権限を定めます。
これにより、業務の効率化と責任の明確化が図れ、組織全体の連携が強化されます。
- 組織図:各部署や役職の関係性を示す。
- 職務権限規程:役職ごとの責任範囲や権限を明確化。
- 稟議規程:稟議書の作成手順や承認フローを規定。
- 関係会社管理規程:子会社や関連会社の管理方法を定める。
就業規則や給与に関する人事労務規定
従業員の労働条件や福利厚生を定める規定です。
就業規則は労働基準法に基づき作成されるもので、給与規程は賃金の計算方法や支払い条件を明確化します。
これらは従業員の安心感を高め、企業の信頼性を向上させる重要な役割を果たします。
- 就業規則:労働条件や勤務時間、休暇制度を規定。
- 賃金規程:給与の計算方法や支払い条件を明確化。
- 退職金規程:退職金の支給基準や計算方法を定める。
- 出張旅費規程:出張時の費用精算方法を規定。
安全衛生管理や文書の取り扱いなど総務関連の規程
企業の安全管理や文書管理を規定するものです。
安全衛生管理規程は従業員の健康と安全を守るための基準を定め、文書取扱規程は重要書類の保存や管理方法を規定します。
これにより、企業の運営がより安全で効率的になります。
- 安全衛生管理規程:職場の安全基準や健康管理方法を定める。
- 文書取扱規程:重要書類の保存期間や管理方法を規定。
- 印章取扱規程:印章の使用範囲や保管方法を明確化。
- 固定資産管理規程:会社資産の管理方法を規定。
関連記事:人事と労務の役割と違いとは?業務内容や年間スケジュール、効率化の方法を解説
経理規程や在庫管理規程等の業務管理
財務や業務の効率化を目的とした規定です。
経理規程は会計処理の基準を定め、在庫管理規程は商品の管理方法を規定します。
これにより、業務の透明性と効率性が向上し、企業の信頼性が高まります。
- 経理規程:会計処理の基準や手続き方法を定める。
- 原価計算規程:原価計算の目的や計算方法を規定。
- 在庫管理規程:商品の棚卸方法や管理基準を明確化。
- 債権管理規程:債権回収の手順や与信限度額を規定。
その他の社内規程
企業の特定の課題に対応するための規定も存在します。
これにより、従業員の働きやすさを向上させ、企業の課題解決に寄与します。
ハラスメント防止規程やSNS利用規程などがその例です。
- ハラスメント防止規程:職場でのハラスメント対策を明文化。
- SNS利用規程:従業員のSNS利用に関するルールを定める。
- 情報セキュリティ規程:機密情報の管理方法を規定。
- 緊急時対応規程:災害や事故発生時の対応手順を明確化。
関連記事:CFO(最高財務責任者)とは?役割と業務内容、CFO人材採用のポイントについて解説
社内規程の作り方

社内規程は、企業の運営を円滑に進めるための重要なツールです。
適切に作成すれば、業務効率化やトラブル防止、従業員の働きやすさの向上につながります。
以下に、社内規程を作成するための具体的な手順を解説します。
①現状分析と目的の明確化
まず、現状の課題を洗い出し、規程を作成する目的を明確にします。
例えば、従業員間のトラブル防止や業務効率化を目指す場合、どのような規程が必要かを具体的に考えることが重要です。
現状分析では、従業員数や業務内容、既存のルールの有無などを確認し、規程作成の方向性を定めます。
②情報の収集
次に、他社の事例や業界標準、関連法令を参考に情報を収集します。
例えば、労働基準法や個人情報保護法など、規程に関連する法律の確認が重要です。
また、従業員へのアンケートやヒアリングを実施し、現場の声を反映させることも効果的で、規程の実効性を高めることができます。
関連記事:企業法務の役割と重要性とは?主な仕事や関連する法律について解説
③草案の作成
収集した情報を基に、規程の草案を作成します。
この段階では、規程の構成や文章表現を考え、わかりやすく具体的な内容を心がけます。
例えば、規程の目的や適用範囲、具体的なルールを明確に記載することで、従業員が理解しやすい内容に仕上げます。
④社内での検討と意見聴取
草案を関係者に確認してもらい、意見や修正点を集めます。
例えば、管理職や従業員代表からのフィードバックを受けることで、規程の実効性を高めることができます。
このプロセスでは、関係者間での議論を通じて、規程の内容をさらにブラッシュアップします。
⑤専門家によるレビュー
法律や規制に抵触しないように、専門家にレビューを依頼します。
例えば、社会保険労務士や弁護士に規程を確認してもらうことで、法的なトラブルの防止につながります。
この段階で、規程の内容を最終的に調整します。
関連記事:コンプライアンスと法務の違いは?業務内容や部門を分けるメリット・デメリットを解説
⑥最終調整と承認
専門家のレビューを基に、規程の最終調整を行い、承認を得ます。
例えば、経営陣や取締役会で規程を正式に承認することで、規程の効力を確保します。
このプロセスでは、規程の内容が企業の方針や目標に合致しているかを確認します。
⑦従業員への周知と説明
承認された規程を従業員に周知し、内容を説明します。
例えば、社内研修や説明会を開催することで、従業員が規程を理解し、遵守するように促します。
また、規程を社内ポータルサイトや掲示板に掲載することで、いつでも確認できる環境を整えます。
⑧運用と見直し
規程を運用し、定期的に見直しを行います。
例えば、業務環境の変化や法改正に対応するため、規程の内容を更新が重要です。
従業員からのフィードバックを受けながら、規程を改善し続けることで、企業の成長を支える基盤を維持します。
関連記事:企業に欠かせないコンプライアンスオフィサーとは?主な業務・必要なスキルについて解説
社内規程を作成する際のポイント

社内規程は、企業運営を円滑に進めるための重要なツールです。
適切な規程を作成することで、業務効率化やトラブル防止、従業員の働きやすさを向上させることができます。
以下に、社内規程を作成する際のポイントを解説します。
作成する優先順位を考慮する
社内規程を作成する際には、優先順位の考慮が重要です。
例えば、法的に作成が義務付けられている就業規則や安全衛生管理規程は、最優先で整備する必要があります。
一方で、企業独自のルールである服装規定やテレワーク規定などは、企業のニーズや課題に応じて作成を進めることができます。
優先順位を明確にすることで、効率的な規程作成が可能になります。
法律に抵触しないようにする
社内規程が法律に抵触しないようにすることは、企業のコンプライアンスを維持するために必要です。
例えば、労働基準法や個人情報保護法など、関連する法令を確認し、規程内容が適法であることを専門家に確認を受けることが重要です。
法律違反を未然に防ぐことで、企業の信頼性を向上させることができます。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
監督官庁へ必要な届出を行う
一部の社内規程は、監督官庁への届出が必要です。
例えば、就業規則は労働基準監督署への届出が義務付けられています。
届出を怠ると法的な問題が発生する可能性があるため、必要な手続きを確実に行うことが必要です。
従業員への周知を徹底する
作成した社内規程を従業員に周知し、内容を理解してもらうことが重要です。
例えば、社内研修や説明会を開催し、規程の目的や具体的な内容を説明することで、従業員が規程を遵守しやすくなります。
また、規程を社内ポータルサイトや掲示板に掲載することで、従業員がいつでも確認できる環境を整えることができます。
定期的に見直しを行い、内容を更新する
社内規程は一度作成して終わりではなく、定期的な見直しが必要です。
例えば、法改正や業務環境の変化に対応するため、規程内容を更新が求められます。
従業員からのフィードバックを受けながら、規程を改善し続けることで、企業の成長を支える基盤の維持ができます。
関連記事:質を向上させるコンプライアンス研修の資料作成方法を解説
社内規程に法的拘束力はある?
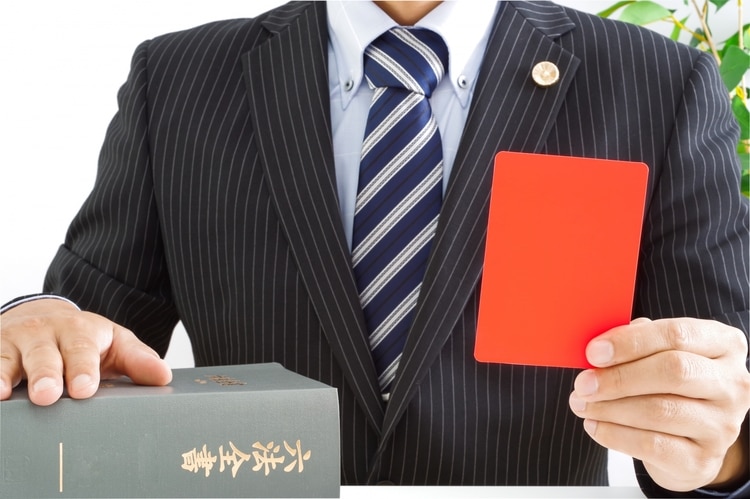
社内規程の法的拘束力は、その性質や内容によって異なります。
例えば、就業規則のように法律で作成が義務付けられているものは、法的拘束力を持ちます。
一方で、企業独自のルールである服装規定やテレワーク規定などは、法的拘束力を持たない場合が一般的です。
しかし、これらの規程も従業員との労使間の慣行として確立されている場合、一定の拘束力を持つことがあります。
また、社内規程が合理的であり、従業員に十分に周知されている場合には、裁判などでその効力が認められることがあります。
例えば、ハラスメント防止規程や情報セキュリティ規程などは、企業のリスク管理やコンプライアンス強化の観点から重要視され、実際の運用が適切であれば法的な効力を持つこともあります。
企業は、規程の内容を明確にし、従業員に理解されるよう努めることが重要です。
これにより、規程の遵守を促進し、トラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、定期的な見直しを行い、最新の法令や業務環境に適応させることで、規程の有効性の維持が求められます。
関連記事:コンプライアンスと心理的安全性の関係とは?見るべきサインや向上させる方法を解説
まとめ
社内規程は、企業の成長や従業員の働きやすさを支える重要な要素です。
適切な作成と運用を行うことで、企業全体の効率化やトラブル防止に寄与します。
定期的な見直しを行い、常に最新の状態の維持が成功の鍵です。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
関連記事:労務コンプライアンスとは?違反事例とチェックポイントを解説