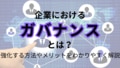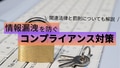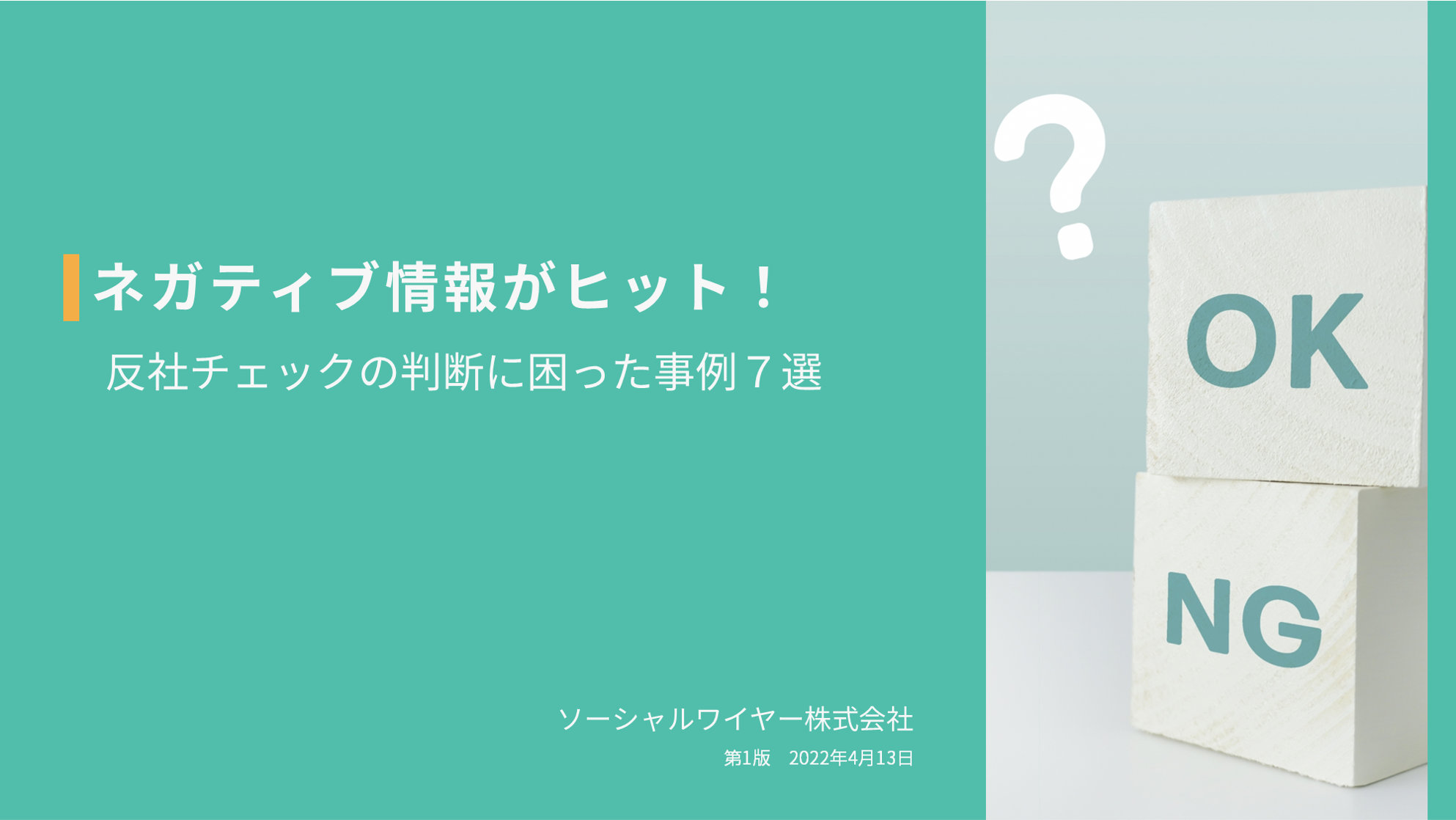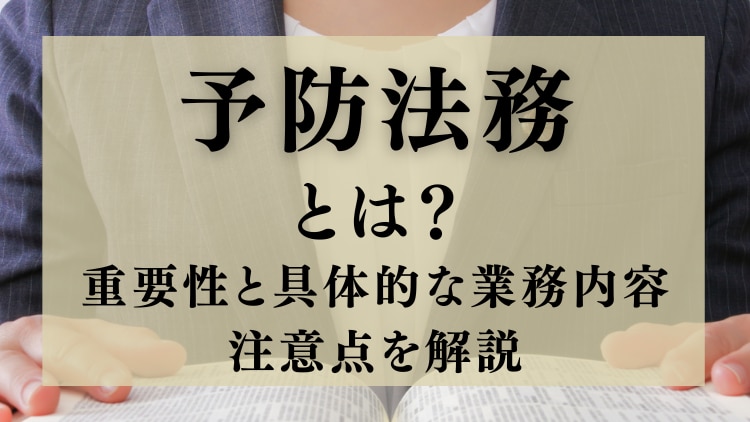
予防法務とは?重要性と具体的な業務内容、注意点を解説
予防法務は、企業が法律問題を未然に防ぐために行う重要な取り組みです。
この記事では、予防法務の基本的な概要から、その重要性や具体的な業務内容、さらには中小企業が取り組む際の注意点までを詳しく解説します。
契約書の管理や社内規程の整備、トラブル予防の方法を知ることで、企業は法的リスクを軽減し、安定した経営基盤を築くことができます。
予防法務を効果的に活用し、トラブルの回避と経営の向上を目指しましょう。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】反社チェックの契約可否の判断に迷った事例
目次[非表示]
- 1.予防法務とは
- 2.予防法務の重要性
- 2.1.コンプライアンスの強化
- 2.2.トラブルの回避
- 2.3.トラブルの影響の最小化
- 3.予防法務の具体的な業務内容
- 3.1.契約書の審査
- 3.2.社内規程の作成・チェック
- 3.2.1.ソーシャルメディア利用規程
- 3.2.2.ハラスメント防止規程
- 3.3.契約書管理規程
- 3.4.特許権・意匠権などの取り扱い
- 3.5.人事・労務管理のサポート
- 3.6.株主総会の準備
- 4.予防法務を効率化する方法
- 4.1.契約書管理の体制を整備する
- 4.2.契約書審査のフローを効率化する
- 5.中小企業が予防法務に取り組む際の注意点
- 5.1.経営者が積極的に取り組む
- 5.2.重要度の高いものから対応する
- 5.3.社内体制を整備する
- 5.4.定期的に法務チェックを行う
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの事例を学ぶ】
予防法務とは

予防法務とは、法律問題が発生する前にこれを未然に防ぐための一連の取り組みを指します。
企業の日常業務や事業活動において潜在的な法的リスクを特定し、それらを回避・軽減する仕組みを整えることを目的としています。
例えば、契約書の適切なチェックや社内規程の整備、従業員へのコンプライアンス教育などがその具体例です。
このような取り組みによって、企業は不要なトラブルを回避し、経営の安定性を向上させることができます。
戦略法務との違い
戦略法務は、企業がビジネス上の競争力を高めたり、新たな事業機会を創出するための法的サポートを重視します。
一方、予防法務はトラブルの芽を摘み、リスク管理を中心に据えています。
つまり、戦略法務が「攻め」の姿勢を取るのに対して、予防法務は「守り」の役割を果たすという点が大きな違いです。
しかし、両者は相互に補完し合い、企業の成長と安定に貢献します。
臨床法務との違い
臨床法務は、発生した法律問題の解決にフォーカスします。
具体的には、紛争解決や裁判対応、危機管理などの業務が含まれます。
一方、予防法務は問題が発生する前にその可能性を取り除くことを目標とします。
臨床法務が「治療」に例えられるなら、予防法務は「予防接種」と言えるでしょう。
この両者をバランスよく活用することで、企業の法務戦略はより強固なものとなります。
関連記事:コンプライアンスと法務の違いは?業務内容や部門を分けるメリット・デメリットを解説
予防法務の重要性

企業が健全かつ安定的に経営を続けていくためには、予防法務が欠かせない存在です。
法律問題の発生を未然に防ぐ取り組みは、企業の成長を支える土台であり、信頼性の向上にも寄与します。
具体的に、予防法務がもたらす重要性を以下の観点から解説します。
コンプライアンスの強化
コンプライアンスの強化は、企業が法令や規則を遵守しながら、社会的責任を果たすための重要な要素です。
予防法務を活用することで、契約書や社内規程を適切に整備し、従業員に対する法的教育を実施することが可能です。
これにより、従業員一人ひとりが法律への意識を高め、企業全体で法令順守の姿勢を貫く体制が構築されます。
関連記事:企業コンプライアンス強化のために必要な「法人の本人確認」とは
トラブルの回避
法律問題が発生すると、企業は多大な時間とコストを費やす必要が生じます。
予防法務では、これらのリスクを事前に把握し、回避するための対策を講じます。
例えば、契約内容の精査やルールの明確化、適切なリスク管理が行われることで、問題が発生する可能性を大幅に減少させることができます。
また、トラブル予兆の段階で適切な対応を行うことで、深刻な問題へと発展することを防ぎます。
トラブルの影響の最小化
問題を完全に防ぐことが難しい場合でも、予防法務の取り組みはその影響を最小限に抑えるために役立ちます。
事前にリスクに対応する準備をしておくことで、問題発生時に迅速かつ効果的な対応が可能になります。
これにより、企業の信用低下を防ぎ、経営の安定を保つことができるのです。
関連記事:労務トラブルとは?発生時の対応手順や注意点、未然に防ぐ対策を解説
予防法務の具体的な業務内容

予防法務は、法律問題を未然に防ぐための多岐にわたる業務を包括します。
企業が法的リスクを減らし、円滑な事業運営を実現するためのサポート役として重要な役割を果たします。
以下に、予防法務の具体的な業務内容を解説します。
契約書の審査
企業活動において契約書は非常に重要な位置を占めますが、内容に潜むリスクを見逃すとトラブルの原因になります。
予防法務では、契約書の条項を専門家がチェックし、不利な条件や法的矛盾点を事前に修正します。
これにより、無用な紛争や損害を未然に防ぐことが可能です。
関連記事:契約法務とは?その役割と具体的な業務内容、重要なポイントをわかりやすく解説
社内規程の作成・チェック
予防法務のもう一つの重要な業務は、企業の運営を支える社内規程の整備です。
社内規程を作成する際は、内容そのものが法律に違反しないようにする必要があります。
社内規程を法的な観点からチェックするのも、予防法務の重要な業務の1つです。
社内規程はさまざまな種類がありますが、例えば以下のような規程があります。
ソーシャルメディア利用規程
従業員のSNS利用におけるトラブルを防ぐため、投稿内容に関するガイドラインを明確にします。
これにより、企業イメージを損なうような不適切な投稿を防止します。
ハラスメント防止規程
職場環境の安全性を保つため、ハラスメント行為の定義や対応フローを策定します。
従業員が安心して働ける環境を構築することに繋がります。
関連記事:IPO準備時に必要な社内規程(社内規定)の整備とは 作成の注意点を具体的に解説
契約書管理規程
契約書の適切な保管や管理は、企業の法的リスクを軽減するために重要です。
予防法務では、契約書管理のための統一した規程を作成し、紛失や情報漏洩を防ぎます。
また、契約更新のスケジュールを管理し、重要な契約を逃さない仕組みを構築します。
特許権・意匠権などの取り扱い
知的財産は企業の競争力の源泉であり、その適切な管理が求められます。
予防法務では、特許権や意匠権を保護し、侵害リスクを事前に特定します。
また、権利の登録や更新手続きのサポートを行い、企業の知的財産を確実に守ります。
関連記事:知財戦略(知的財産戦略)とは?得られる効果と進め方、注意点についてわかりやすく解説
人事・労務管理のサポート
労働基準法に基づいて従業員の権利を保護するための対応を行います。
例えば、従業員の労働条件の見直しや給与体系の適切化などが含まれます。
また、採用や退職時のトラブルを防ぐためのアドバイスも提供します。
株主総会の準備
株主総会における法的問題を回避するために、事前の準備が欠かせません。
予防法務では、株主総会で必要となる書類作成や議事運営の計画をサポートし、円滑な進行を可能にします。
この取り組みにより、株主の信頼を得て企業の成長を支えることができます。
関連記事:人事と労務の役割と違いとは?業務内容や年間スケジュール、効率化の方法を解説
予防法務を効率化する方法

予防法務を効率化することは、企業が法的リスクを抑えながら、迅速かつ効果的に業務を進める上で重要です。
ここでは、効率化を図るための具体的な方法を解説します。
契約書管理の体制を整備する
契約書は企業活動における重要な文書であり、その適切な管理が予防法務の基盤となります。
まずは契約書を一元管理するシステムを導入することが効果的です。
例えば、契約書をデジタル化してクラウド上で管理することで、場所を問わずアクセス可能となり、作業効率を向上させることができます。
また、契約書の検索機能を充実させることで、必要な情報を迅速に取得可能にすることができます。
さらに、期限管理機能を活用することで契約更新の漏れを防ぎ、法的リスクを軽減することが可能です。
関連記事:IPO準備&急成長ベンチャーに必要な「契約管理」 法務体制強化でリスク管理
契約書審査のフローを効率化する
契約書審査は予防法務の中核業務ですが、そのプロセスを効率化することが求められます。
まず、標準化された契約書のテンプレートを作成することで、何度も同じ内容のチェックを行う手間を削減できます。
このテンプレートには、法的リスクの少ない条項や推奨される文言を盛り込むことが重要です。
また、契約書審査を行う際にはワークフローシステムを活用し、関係者間の確認や承認プロセスをスムーズに進めることが効果的です。
システムを利用することで、進捗状況の可視化が可能となり、処理の遅延を防ぐことができます。
関連記事:契約書レビューとは?具体的な流れや確認すべきポイントをわかりやすく解説
中小企業が予防法務に取り組む際の注意点

中小企業にとって、予防法務はトラブルを未然に防ぎ、安定した経営を実現するために欠かせない取り組みです。
しかし、その実践においては特有の課題や注意点があります。
以下では、予防法務を効果的に進めるためのポイントを解説します。
経営者が積極的に取り組む
予防法務は、経営者自身が積極的に関与する姿勢が欠かせません。
中小企業ではリソースが限られているため、経営陣が予防法務の重要性を理解し、取り組みを推進する役割を担う必要があります。
経営者自らが法務の優先度を設定し、従業員に対してコンプライアンスの重要性を共有することで、組織全体での意識改革を図ることが可能です。
重要度の高いものから対応する
中小企業では、リソース不足により全ての法務課題に対応するのは難しい場合があります。
そのため、まずは重要度の高い領域から着手することが効果的です。
例えば、頻繁に発生する契約関連のリスクや、労働問題に関わる規程の整備など、企業活動に直接的な影響を及ぼす分野を優先的に対応しましょう。
これにより、限られたリソースを効率的に活用することが可能です。
関連記事:バックオフィス業務とは?具体的な業務内容と課題、効率化する方法を解説
社内体制を整備する
予防法務を実効性のあるものにするためには、社内体制の整備が必要です。
例えば、法務担当者を選任したり、外部の専門家や弁護士と連携する仕組みを構築することが考えられます。
また、従業員への法的教育を実施し、基本的なコンプライアンス意識を浸透させることも重要です。
明確な役割分担と適切な教育により、効率的な対応が実現できます。
定期的に法務チェックを行う
一度整備した法務体制や規程がそのまま有効とは限りません。
法律の改正や社会情勢の変化に対応するため、定期的に法務チェックを実施することが求められます。
契約書や規程の内容を見直し、最新の法律や企業の現状に即した形にアップデートすることが必要です。
こうしたチェックを怠ると、リスクが蓄積し、大きなトラブルに繋がる可能性があります。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
まとめ
予防法務は、企業が法律問題を未然に防ぎ、安定した経営を実現するために不可欠な取り組みです。
効率的な体制を整え、中小企業でも適切に取り組むことが重要です。
トラブルを防ぐことにより、経営リスクを減少させ、信頼性を向上させることができます。
関連記事:反社会的勢力に関する法律はある?各業界の対策と反社との取引を回避する方法も解説
関連記事:反社会的勢力と知らずに契約を結んでしまった場合に無効にできる?