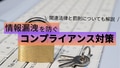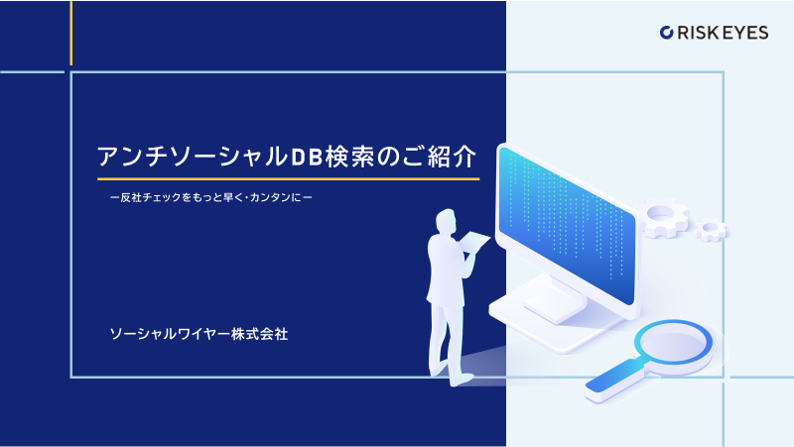企業の義務である障害者雇用 2024年改正「障害者雇用促進法」について詳しく解説
2024年に改正された「障害者雇用促進法」では、企業に課される障害者雇用の義務と責任がさらに強化されました。
法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化など、障害者が働きやすい環境の整備が一層進められています。
この記事では、この改正の背景や具体的な内容、企業が取り組むべきポイントを詳しく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
👉雇用とは?法律上の定義や雇用形態の種類、必要な対応の流れをわかりやすく解説
👉反社チェック(コンプライアンスチェック)を無料で行う方法
👉「採用」時のバックグラウンドチェックとは 必要性とメリット・デメリットについて解説
注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索
目次[非表示]
- 1.障害者雇用は企業の義務である
- 1.1.障害者雇用義務の対象となる企業
- 1.2.障害者雇用が義務付けられた背景
- 2.障害者雇用を義務付けている「障害者雇用促進法」の概要と2024年の改正内容
- 2.1.目的と理念
- 2.2.法定雇用率の段階的な引き上げ
- 2.2.1.雇用率・必要雇用数の計算方法
- 2.3.短時間勤務者も雇用率に算入
- 2.4.精神障害・発達障害者も雇用義務対象範囲に
- 2.5.合理的配慮の提供が義務化
- 3.法定雇用率を満たしていない場合はどうなるか
- 3.1.納付金の支払い義務が発生する
- 3.2.行政指導の対象になる
- 3.3.企業名が公表される
- 4.企業が障害者を雇用する際の注意点
- 4.1.社内で人的・物的な受け入れ態勢を整える
- 4.2.業務上のミスマッチを防ぐ
- 4.3.周囲の従業員に過度な負担をかけないようにする
- 5.障害者が不足している場合の採用方法
- 5.1.ハローワークに求人を掲載する
- 5.2.有料の媒体で求人広告を出す
- 5.3.特別支援学校へ求人票を出す
- 5.4.障害者雇用支援サービスを利用する
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】
障害者雇用は企業の義務である

障害者雇用は、企業が担う重要な社会的責任の一つです。
この責任は「障害者雇用促進法」により、法的に義務付けられています。
同法では、一定規模の企業に対し障害者を雇用し、法定雇用率を満たすことが求められています。
この法律は、障害者が安心して働ける環境を整えると同時に、企業の多様性を促進し、社会全体の調和と発展に寄与することを目的としています。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
障害者雇用義務の対象となる企業
障害者雇用促進法に基づき、常時雇用する労働者が40人以上の企業には、法定雇用率を満たす障害者を雇用する義務があります。
2024年の改正により、法定雇用率が2.5%に引き上げられ、さらに広範な企業が対象となりました。
この義務は、障害者が持つ能力を社会で活かし、経済的な自立を支援するための仕組みです。
障害者雇用が義務付けられた背景
障害者雇用が義務化された背景には、障害者が社会で活躍できる場を提供し、彼らの権利を守るという目的があります。
障害者は、多くの才能や特性がありながらも、働く環境が整わないことでその能力が十分に発揮されない場合がありました。
そのため、障害者雇用促進法が策定され、企業に対して雇用義務が課されることで、障害者が働きやすい環境を整える動きが進んでいます。
このような法整備によって、障害者の社会参加が促進されるとともに、企業や社会全体の成長につながることが期待されています。
関連記事:トライアル雇用とは?雇用の流れやメリット・デメリットを解説
障害者雇用を義務付けている「障害者雇用促進法」の概要と2024年の改正内容

障害者雇用促進法は、障害者の職業安定と社会参加を促進するために制定された法律です。
この法律は、企業に対して障害者を雇用する義務を課し、障害者が働きやすい環境を整えることを目的としています。
2024年の改正では、法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化など、障害者雇用をさらに推進するための重要な変更が行われました。
目的と理念
障害者雇用促進法は、障害者が職業を通じて経済的自立を果たし、社会で活躍できる環境を整えることを目的としています。
この法律の理念は、すべての人が能力を発揮できる職場環境を実現し、多様性と包摂性のある社会を推進することにあります。
企業は、この法のもとで障害者の特性や能力を活かし、持続可能な社会作りに貢献する責任を担っています。
法定雇用率の段階的な引き上げ
2024年4月から法定雇用率が2.5%に引き上げられ、さらに2026年には2.7%に達する予定です。
これにより、障害者の雇用機会が拡大し、より多くの障害者が社会に参加できる環境が整うと期待されています。
企業は、法定雇用率を満たすだけでなく、多様な人材を活用し、新たな価値を創造する意識が重要です。
雇用率・必要雇用数の計算方法
法定雇用率は、常用労働者数に対する障害者の割合を示します。
例えば、従業員数が100人の場合、法定雇用率2.5%に基づき、最低2人の障害者を雇用する必要があります。
この計算方法により、各企業は具体的な採用計画を策定しやすくなります。
関連記事:雇用リスクとは?リスクの種類や低減する方法をわかりやすく解説
短時間勤務者も雇用率に算入
短時間勤務者(週10~20時間勤務)も法定雇用率の計算に含まれるようになりました。
この改正により、さまざまなライフスタイルの障害者が雇用機会を得やすくなり、多様な働き方を支援する動きが強化されています。
精神障害・発達障害者も雇用義務対象範囲に
2024年の改正により、精神障害者や発達障害者も雇用義務の対象に含まれるようになりました。
これにより、企業はさらに幅広い障害者を積極的に雇用し、社会全体の包括性を高める努力が求められています。
合理的配慮の提供が義務化
合理的配慮の提供が企業に義務付けられました。
これには、職場環境のバリアフリー化、適切な業務分担、障害者の特性に応じた支援の提供が含まれます。
これにより、障害者が安心して働ける環境づくりが法的に求められています。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?加入するメリット・デメリットや企業への罰則も解説
法定雇用率を満たしていない場合はどうなるか

障害者雇用促進法に基づき、企業は法定雇用率を満たす障害者を雇用する義務があります。
しかし、この義務を果たせない場合、企業にはさまざまなペナルティが課される可能性があります。
これらの措置は、障害者の雇用を促進し、社会全体での障害者の活躍を支援するために設けられています。
納付金の支払い義務が発生する
法定雇用率を達成していない企業には、障害者雇用納付金の支払い義務が発生します。
この納付金は、法定雇用率を達成できていない人数に応じて計算され、企業規模が100人以上の場合に適用されます。
例えば、不足している障害者1人につき月額5万円が徴収される仕組みです。
この納付金は、障害者雇用を促進するための財源として活用されます。
関連記事:採用担当者必見!中途採用の成功事例と成功させるポイントを徹底解説
行政指導の対象になる
法定雇用率を満たしていない企業には、ハローワークを通じて行政指導が行われます。
具体的には、障害者を雇用するための計画を作成し、その計画に基づいて雇用を進めるよう指導されます。
計画が適切に実施されない場合には、さらに厳しい指導が行われることがあります。
これにより、企業が障害者雇用に積極的に取り組むよう促されます。
企業名が公表される
最終的に法定雇用率を満たさない場合、企業名が公表される場合があります。
この公表は、厚生労働省のホームページなどで行われ、社会的な影響を与える可能性があります。
企業名が公表されることで、企業イメージの低下や採用活動への悪影響が懸念されます。
また、社員のモチベーション低下や離職率の増加といった内部的な問題も引き起こされる可能性があります。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?必須項目や2024年法改正に伴う変更点について解説
企業が障害者を雇用する際の注意点

障害者雇用は、企業が多様性を尊重し、社会的責任を果たす重要な取り組みです。
しかし、障害者が安心して働ける環境を整えるためには、いくつかの注意点があります。
以下では、具体的なポイントを解説します。
社内で人的・物的な受け入れ態勢を整える
障害者が働きやすい環境を整えるためには、社内での人的・物的な受け入れ態勢が不可欠です。
例えば、バリアフリー化されたオフィスや、障害者が使用しやすい設備の導入が求められます。
また、障害者の特性やニーズに応じた業務内容や勤務時間の調整も重要です。
さらに、障害者をサポートする担当者を配置し、日常的な相談や支援を行える体制を整えることで、安心して働ける環境を提供できます。
関連記事:スタートアップに求められるIPO準備で早く取り組むべき組織体制の整備とは
業務上のミスマッチを防ぐ
障害者の能力や特性に合った業務を割り当てることは、雇用の成功において重要な要素です。
業務内容が障害者のスキルや体力に合わない場合、ストレスや業務効率の低下を招く可能性があります。
そのため、採用時には適性検査や面談を通じて、障害者の得意分野や希望を把握することが大切です。
また、業務内容を定期的に見直し、必要に応じて調整を行うことで、長期的な雇用関係を築くことができます。
周囲の従業員に過度な負担をかけないようにする
障害者を雇用する際には、周囲の従業員への配慮も欠かせません。
障害者のサポートに過度な負担がかかると、職場全体の士気や生産性に影響を与える可能性があります。
そのため、事前に従業員全体への研修を実施し、障害者への理解を深めることが重要です。
また、業務の分担やサポート体制を明確にし、全員が無理なく協力できる環境を整えることが求められます。
関連記事:採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックとは?メリット・デメリットについて解説
障害者が不足している場合の採用方法

障害者雇用を進める上で、適切な人材を確保することは重要な課題です。
法定雇用率を満たすためには、積極的な採用活動が必要です。
以下では、障害者を採用するための具体的な方法を解説します。
ハローワークに求人を掲載する
ハローワークは、障害者雇用を支援するための重要な窓口です。
企業はハローワークに求人を掲載することで、障害者求職者に直接アプローチすることができます。
ハローワークでは、障害者向けの専門窓口や職業相談員が配置されており、企業と求職者のマッチングをサポートします。
また、採用後のフォローアップも行われるため、安心して利用できます。
有料の媒体で求人広告を出す
有料の求人媒体を活用することで、より広範な求職者にアプローチすることが可能です。
特に、障害者雇用に特化した求人サイトや専門誌を利用することで、ターゲット層に直接情報を届けることができます。
有料媒体は、企業の採用ニーズに応じたカスタマイズが可能であり、効率的な採用活動を実現します。
関連記事:採用戦略とは?進め方やメリット、ポイントをわかりやすく解説
特別支援学校へ求人票を出す
特別支援学校は、障害者の教育と就労支援を行う機関です。
企業が特別支援学校に求人票を提出することで、卒業予定の生徒やその保護者に直接アプローチすることができます。
学校側も、生徒の特性や能力を理解しているため、企業とのマッチングをスムーズに進めることが可能です。
また、インターンシップや職場見学を通じて、採用前にお互いの理解を深めることも効果的です。
障害者雇用支援サービスを利用する
障害者雇用支援サービスは、企業が障害者を採用し、職場に定着させるための専門的な支援を提供します。
これらのサービスでは、採用活動のサポートだけでなく、職場環境の整備や従業員への研修も行われます。
例えば、地域障害者職業センターや民間の支援機関を活用することで、採用活動を効率化し、障害者が働きやすい環境を整えることができます。
関連記事:解雇するための条件とは?主な解雇理由や解雇後の注意点についてわかりやすく解説
まとめ
2024年の改正により、「障害者雇用促進法」はさらに強化されました。
法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化など、障害者が働きやすい環境が整備されつつあります。
企業は単なる義務履行に留まらず、積極的に障害者雇用を推進することが必要です。
これらの取り組みは、障害者の社会参加が進むだけでなく、企業側も多様性のある職場環境の構築にもつながります。
ダイバーシティとインクルージョンが進展する社会は、企業と社会全体の双方にとって持続可能な未来への重要な一歩となるでしょう。
関連記事:採用コストの相場はどのくらい?中途・新卒採用の平均コストや計算方法、コスト削減のポイントを解説
関連記事:リファラル採用とは?目的やメリット・デメリット、成功させるポイントをわかりやすく解説