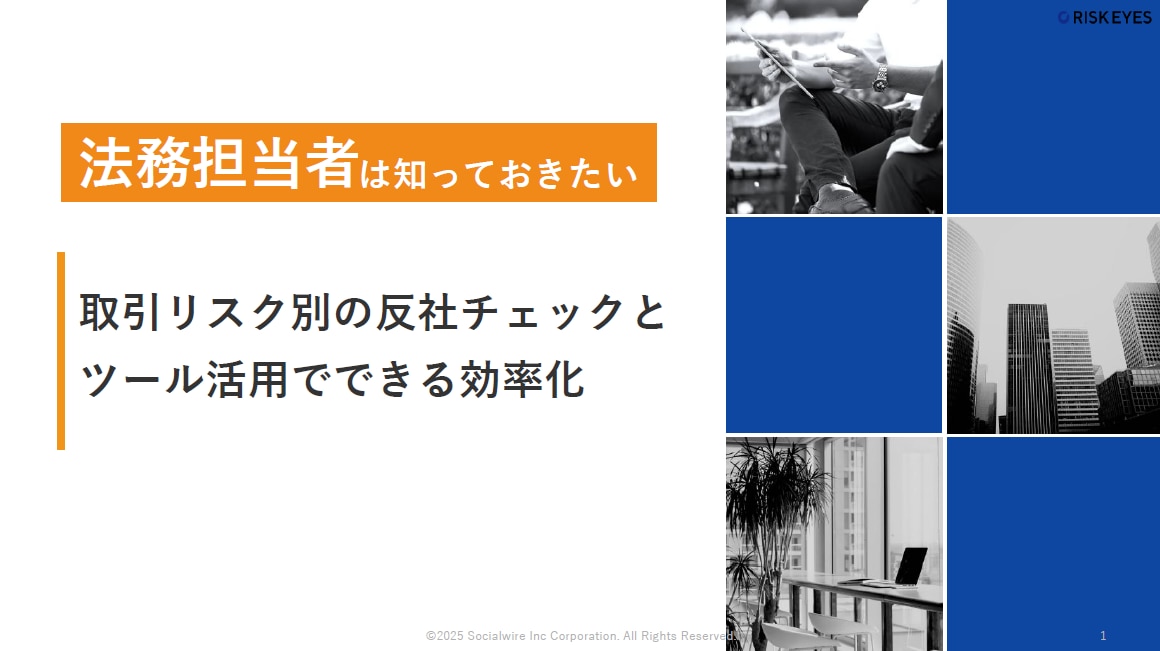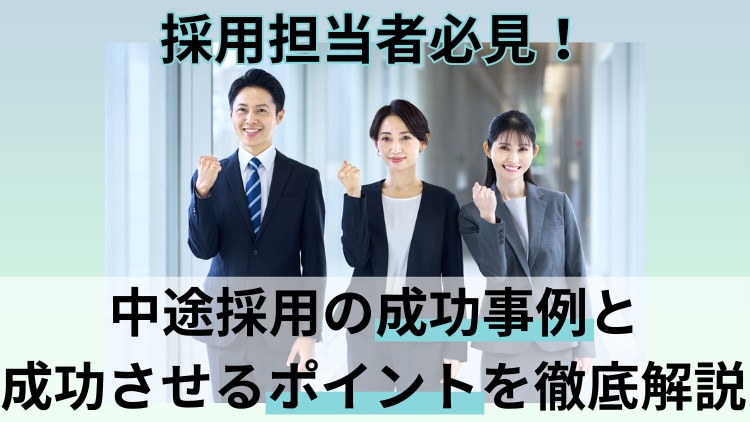
採用担当者必見!中途採用の成功事例と成功させるポイントを徹底解説
中途採用の成功は企業成長の鍵ですが、売り手市場や採用競争の激化など多くの課題が立ちはだかります。
この記事では、具体的な成功事例と共に、中途採用を成功させるための重要なポイントを徹底解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
【実務担当者】取引リスク別反社チェック効率化の方法
目次[非表示]
- 1.中途採用の現状
- 2.中途採用の成功事例
- 2.1.大手製造業
- 2.2.従業員規模20名のIT企業
- 2.3.新規事業を始めるサービス業
- 2.4.営業担当を求める社会保険労務士事務所
- 3.中途採用が難しい7つの理由
- 3.1.有効求人倍率の上昇
- 3.2.即戦力人材が転職市場に出てこず競争率が高い
- 3.3.企業の知名度に左右される
- 3.4.人材の見極めが難しい
- 3.5.選考期間が短い
- 3.6.面接・内定辞退の増加
- 3.7.早期退職の増加
- 4.中途採用を成功させるポイント
- 4.1.売り手市場なことを採用に関わる全員で理解する
- 4.2.自社と競合を理解して採用ターゲットを定める
- 4.3.自社に合う採用手法を選定する
- 4.4.選考のリードタイムを短くする
- 4.5.面接では動機づけを意識する
- 4.6.ネットの口コミを活用・評価を向上させる
- 4.7.入社後フォローを十分に行う
- 5.中途採用に欠かせない反社チェックとは
- 5.1.反社チェックの方法
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【無料で反社チェックの効率化を学ぶ】
中途採用の現状

現在の中途採用市場は、多くの企業にとって重要な課題となっています。
特に少子高齢化や労働力人口の減少により、企業間での優秀な人材を巡る競争が激化しています。
社会の急速な変化に適応しながら採用活動を成功させるためには、正確な転職市場の現状理解が不可欠です。
転職は売り手市場
現代の転職市場は「売り手市場」が続いており、求職者が企業を選ぶ立場にあります。
有効求人倍率が高止まりしている現状では、特に専門スキルを持つ即戦力人材を巡る競争が熾烈です。
また、コロナ禍をきっかけにリモートワークや柔軟な働き方が広がり、求職者の意識も大きく変化しました。
単なる高給与や福利厚生だけでなく、職場の価値観や働きやすさ、ワークライフバランスなども転職先を選ぶ重要な基準となっています。
このような状況下で、企業側は自社の魅力を最大限アピールする必要があります。
例えば、独自性のある働き方やキャリア形成の機会を提供することが、求職者の心を掴む鍵になるでしょう。
関連記事:採用戦略とは?進め方やメリット、ポイントをわかりやすく解説
採用単価は上昇傾向
売り手市場の影響を受け、採用単価は年々上昇しています。
求人広告費用、採用エージェントの手数料、そして内定者フォローに必要なコストなど、採用活動にかかる費用の増加は企業にとって大きな負担です。
さらに、採用スピードを上げるために選考プロセスの効率化を図ることも、新たな投資を必要とします。
また、早期離職を防ぐためのフォローアップや、入社後の研修プログラムの強化も重要な課題です。
これらの取り組みにより、長期的な観点で人材を定着させることが可能となりますが、同時に採用活動全体のコストがさらに増大するリスクも伴います。
関連記事:採用コストの相場はどのくらい?中途・新卒採用の平均コストや計算方法、コスト削減のポイントを解説
中途採用の成功事例

中途採用は即戦力の人材を確保するために非常に重要な活動です。
企業の特徴や課題に応じた柔軟なアプローチを取ることで、採用活動を成功させる事例が数多くあります。
ここでは、4つの具体的な成功事例をご紹介します。
大手製造業
ある大手製造業の企業で、高度な技術力を誇るエンジニアを採用するために、社内見学ツアーや体験型イベントを実施した例をご紹介します。
イベントの内容として、最新設備を活用した実際の作業現場を候補者に見せたり、社員が直接仕事の魅力を語る座談会を行ったりしました。
これにより、候補者は企業の環境や働きがいを具体的にイメージでき、ミスマッチを防ぐことができました。
結果として、業界内で他社に負けない優秀な人材を採用し、長期的な戦力として活用することができたことで、成功した一例と言えます。
従業員規模20名のIT企業
地方に拠点を構える従業員20名のIT企業では、大企業との差別化のため「フルリモート勤務」や「自由な勤務時間」を打ち出した例を紹介します。
企業の拠点とは違う北海道在住のエンジニアや、子育て中のスキル保有者にも応募可能な求人を作成し、全国規模で応募者を募りました。
さらに、SNS上で現場社員の声や日常業務を発信し、フラットな社風やチームの一体感を強調することで、求職者の興味を引きました。
その結果、首都圏から遠隔で働きたい優秀な人材を採用することに成功した一例と言えます。
関連記事:採用プロセスとは?設計するメリットや一般的な流れ、ポイントをわかりやすく解説
新規事業を始めるサービス業
新規事業を立ち上げる際は、スピードが非常に重要です。
この企業は、既存社員から推薦を受けるリファラル採用を活用し、信頼性の高い候補者を迅速に確保した例です。
また、前職でのスキルや信頼関係が既に確認できている候補者に絞り込むことで、面接プロセスを簡略化しました。
さらに、新規事業の具体的なビジョンを候補者に丁寧に説明し、「この事業を一緒に育てたい」と強く動機づけすることで、短期間でマッチする人材を採用することに成功した一例です。
営業担当を求める社会保険労務士事務所
ある社会保険労務士事務所が、営業担当者を採用するために、地元志向の人材に特化した戦略を取った例を紹介します。
この企業では、地元の合同企業説明会に参加し、求職者に直接働き方や業務内容を説明しました。
また、採用サイトに顧客との関わりや具体的な成功事例を紹介するページを設け、「人と人を繋ぐ仕事の魅力」を伝えました。
結果、地元に密着した経験を持つ営業担当者を採用し、地域での顧客ネットワークをさらに強化することができた成功例です。
関連記事:IPO準備企業が転職者を中途採用する際に気を付けるべきこと
中途採用が難しい7つの理由

中途採用は即戦力を確保する重要な手段ですが、多くの企業がその難しさに直面しています。
ここでは、中途採用が難しいとされる7つの理由を詳しく解説します。
有効求人倍率の上昇
日本の転職市場は「売り手市場」となっており、有効求人倍率は高止まりしています。
この状況では、求職者が複数の選択肢を持つため、企業は他社と競争しながら魅力的な条件を提示する必要があります。
特に専門職や技術職では需要が供給を上回り、採用がますます困難になっています。
即戦力人材が転職市場に出てこず競争率が高い
即戦力となる人材は、高いスキルや経験を求められる一方で、転職市場に出てくる機会が少ないのが現状です。
これにより、企業は同じ人材を求めて競争することになり、採用コストが増大します。
また、こうした人材は現職の待遇が良いことが多く、転職を引き留められるケースも少なくありません。
関連記事:採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックとは?メリット・デメリットについて解説
企業の知名度に左右される
中小企業やスタートアップは、大企業と比較して知名度が低いため、求職者からの認知度が不足しがちです。
知名度が低いと、求職者にアプローチできる範囲が限られ、結果的に応募者数が少なくなるという課題があります。
魅力的な企業文化や制度があっても、それが十分に伝わらないと採用活動が思うように進まない場合があります。
人材の見極めが難しい
書類選考や短時間の面接だけでは、候補者の能力や適性を見極めることは難しいです。
特に転職希望者が多くの企業を並行して受けている場合、企業側は短期間で採用判断を迫られることが多く、ミスマッチが発生しやすくなります。
このため、採用後の早期離職リスクが高まる可能性もあります。
関連記事:日本版DBSとは?イギリスとの違いや採用における反社チェックについても解説
選考期間が短い
売り手市場の中では、迅速な選考が求められますが、短期間で候補者のすべてを把握することは難しいです。
他社に先を越されないよう、選考を急ぐあまり、十分な検討が行われないケースが増えています。
その結果、人材の質が低下したり、フィットしない人材を採用してしまうリスクも存在します。
面接・内定辞退の増加
現在の市場環境では、候補者が複数の内定を持つことが珍しくありません。
そのため、選考途中で面接を辞退されるケースや、内定を出しても辞退されるケースが増えています。
企業にとっては時間とリソースの無駄となるだけでなく、採用計画の遅れにも繋がります。
早期退職の増加
採用後、短期間で退職される「早期退職」の問題も深刻です。
採用プロセスにおけるミスマッチが原因であることが多く、これにより企業は再び採用活動を行う必要に迫られます。
結果として、コスト増加や人員不足の悪循環が発生します。
関連記事:採用管理システム(ATS)とは?基本機能や導入するメリット、選定のポイントを解説
中途採用を成功させるポイント

中途採用は即戦力人材を確保するために重要な活動ですが、売り手市場の中では困難も伴います。
ここでは、中途採用を成功させるための具体的なポイントを解説します。
売り手市場なことを採用に関わる全員で理解する
現在の転職市場は売り手優位であり、求職者が企業を選べる状況が続いています。
この現状を採用に関わるすべての社員が共有することが重要です。
人事部門だけでなく、現場の採用担当者や経営層も市場環境を理解し、一貫性のある採用戦略を構築することが成功のカギとなります。
自社と競合を理解して採用ターゲットを定める
競合他社の採用戦略や条件を分析し、自社の強みを把握することは効果的な採用に繋がります。
例えば、給与や福利厚生が競合と同等でない場合でも、働き方の柔軟性やキャリア形成の機会をアピールすることで差別化を図ることが可能です。
ターゲットとする求職者像を明確化し、ピンポイントでアプローチを行いましょう。
関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説
自社に合う採用手法を選定する
ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、求人媒体の活用など、採用手法は多岐にわたります。
自社の規模や業界特性、採用対象者に最適な手法を選ぶことで、コストを抑えながら効率的に人材を確保することができます。
選考のリードタイムを短くする
市場競争が激化する中、候補者が他社に流れてしまうのを防ぐために、選考プロセスを迅速化する必要があります。
書類選考や面接のスケジュールを効率化し、内定までのリードタイムを短縮することで、他社との差別化を図りましょう。
面接では動機づけを意識する
面接は単に候補者を見極める場ではなく、入社意欲を高める重要な機会でもあります。
候補者のスキルや経験を評価するだけでなく、企業の魅力やビジョンを具体的に伝えることで、彼らのモチベーションを引き出すことが可能です。
関連記事:リファラル採用とは?目的やメリット・デメリット、成功させるポイントをわかりやすく解説
ネットの口コミを活用・評価を向上させる
求職者は転職先を選ぶ際、インターネット上の口コミや評価を参考にすることが多いです。
そのため、自社の評判を定期的にチェックし、ネガティブなコメントには適切に対応することが求められます。
また、社員の声を積極的に発信することで、企業の魅力を広くアピールすることができます。
入社後フォローを十分に行う
入社後のフォロー体制を整えることで、早期退職を防ぐとともに、社員のエンゲージメントを高めることができます。
具体的には、メンター制度を導入したり、定期的な面談を実施したりして、新入社員が職場にスムーズに馴染めるよう支援することが大切です。
関連記事:人材マネジメントとは?その内容や必要性、ポイントを解説
中途採用に欠かせない反社チェックとは

中途採用を進める上で、企業が避けるべきリスクの一つが反社会的勢力との関わりです。
反社会的勢力への関与が疑われる人材を採用してしまうと、企業の信用が損なわれるだけでなく、法的トラブルに発展する可能性もあります。
そのため、候補者が反社会的勢力と無関係であることを確認する「反社チェック」は、採用活動において重要なプロセスの一環となります。
関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説
反社チェックの方法
反社チェックの方法はいくつかあります。
採用時の反社チェックの場合、まず、採用候補者の経歴や職務経歴書を精査し、不審な点がないか確認します。
さらに、過去の勤務先や所属団体についても調査を行い、反社会的勢力との関わりがないかを確認します。
インターネット検索での調査も可能ですが、不要な情報が大量にヒットしてしまうだけでなく、情報の信頼性を精査するのに、多くの手間と時間がかかります。
ある程度まとまった人数の採用を行う際は、反社チェックツールを導入することを推奨します。
また、自社での調査のみでは不安な場合は、外部の専門機関に依頼して、応募者の反社チェックを実施することも効果的です。
より詳細な調査が行え、企業にとってリスクのある人物の採用を防ぐことができます。
関連記事:反社チェックに引っかかるケースとは?チェックが必要な理由と対策を解説
まとめ
中途採用を成功させるには、現状を正確に把握し、企業の魅力を効果的に伝えることが重要です。
売り手市場の状況下で採用ターゲットを明確化し、適切な採用手法を選ぶことで、優秀な人材を獲得できます。
また、迅速な選考と動機づけ、口コミ評価の向上、入社後フォローの充実が成功の鍵です。
さらに、反社チェックを徹底することでリスクを回避し、長期的な信頼関係を築ける人材を確保することができます。
これらのポイントを押さえた採用活動が、企業の成長を支えるでしょう。
関連記事:労働契約とは?基本原則やルール、よくあるトラブルや禁止事項をわかりやすく解説
関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説