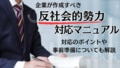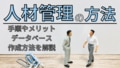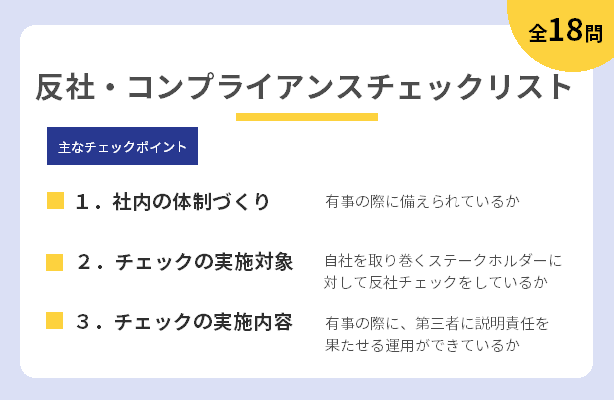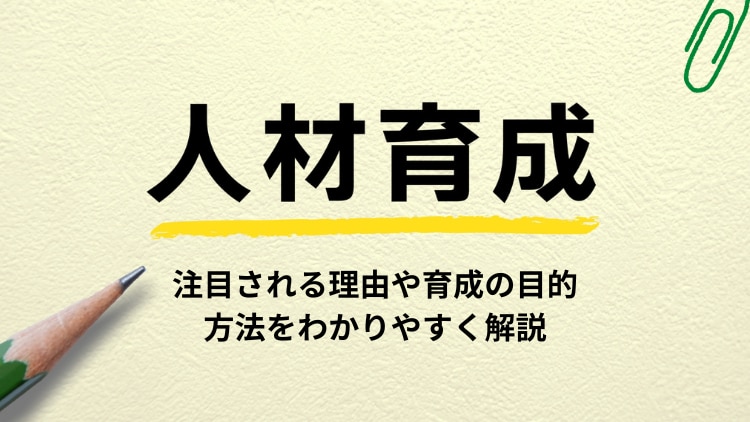
人材育成とは?注目される理由や育成の目的、方法をわかりやすく解説
人材不足が深刻化する現代において、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、企業を成長させるために、人材育成が欠かせません。
人材育成と聞くと研修を想像しがちですが、基本的な考え方を理解すれば、研修だけでは人材育成は行えないということがわかります。
この記事では、人材育成とは何か、注目される理由や育成を行う目的、その方法についてわかりやすく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら
目次[非表示]
- 1.人材育成とは
- 2.人材育成が注目される理由
- 3.人材育成の目的
- 3.1.スキルや知識の向上
- 3.2.生産性の向上
- 3.3.人材の流出防止
- 3.4.リーダーシップの育成
- 3.5.従業員のキャリア開発・自己実現
- 4.人材育成の方法
- 5.人材育成のポイント
- 5.1.目的を明確にする
- 5.2.経営陣・部門担当者・人事が連携する
- 5.3.階層別に適した方法を取る
- 5.4.実践の機会とサポート体制を整備する
- 5.5.指導側の育成も行う
- 5.6.進捗・成果を可視化する
- 6.まとめ
人材育成とは

人材育成とは、企業の経営目標の達成や、成長・発展に貢献できるような人材を育てることです。
スキルや技術の習得を促進し、人材を企業が思い描く方向へ成長させるための取り組みです。
職種や役職、入社年数などで対象者を分けて、研修などさまざまな育成方法で、一律のスキル習得を目指します。
人材教育との違い
人材教育は、スキルや知識を教えること自体を指します。
人材育成の方法は、教育以外に経験を通じて育成を行う方法もあります。
人材育成の手段の1つとして人材教育が存在するというような位置づけです。
人材開発との違い
人材開発は、英語の「Human Resource Development」=「人的資源の開発」から生まれた言葉です。
人材育成は、単に人を育てるという意味ですが、人材開発は、人材を経営資源と捉え、能力を最大限に発揮できるよう開発するという意味します。
人材を経営資源と捉え、能力を最大限に発揮できるよう開発することを意味します。
関連記事:人事制度とは?3本柱とその役割、制度構築のフローを解説
人材育成が注目される理由

人材育成が注目されている背景には、主に以下の2つの理由があります。
- 役割の多様化
- 人材不足
企業が成長し続け、競合他社に勝つためには人材育成が欠かせない時代となっています。
それぞれの理由を詳しく解説します。
役割の多様化
これまでの人材市場では、定期的に人材の確保ができるうえ、大手企業などでは人員数に余裕があったため、従業員一人ひとりの役割が明確になっていました。
しかし、近年の深刻な人手不足により、その余裕が失われつつあります。
こういった状況において、それぞれの従業員が受け持つ業務の範囲が多岐にわたり、一人ひとりの役割が多様化しています。
一部業務においては未経験の業務も含まれるため、従来どおりのパフォーマンスを発揮できないこともあります。
また、働き方改革が進み、残業の抑制や就業時間の短縮など労働環境が変化しています。
そのため、企業は従業員のパフォーマンスを高めて生産性を向上させることが必要不可欠であり、人材育成が注目されています。
関連記事:雇用契約書は必要か?交付方法や内容、作成時のポイントについても解説
人材不足
前述の通り、近年は人材不足が深刻化しています。
特に、中小企業やスタートアップ企業は人手不足に悩まされている企業も多いでしょう。
これまでは人手が足りているため、計画的に人材育成を行わなくても、各部署や現場に任せることでば人が自然に育つ環境でした。
そのため、全社的に人材育成に取り組んでいなかった企業も少なくありません。
しかし、人手不足である今、部署や現場任せの人材育成は限界を迎えています。
人材不足により、企業全体を巻き込んで計画的な人材育成を行うことが必要となっているということです。
関連記事:2024年11月施行!フリーランス新法の具体的な内容とは?違反した場合の罰則や企業がとるべき対応を解説
人材育成の目的

人材育成の最大の目的は、企業全体の競争力や成果を高めることです。
そのための具体的な目的について5つ解説します。
スキルや知識の向上
人材育成の目的として最初に挙げられるのが、スキルや知識の向上です。
業務に必要なスキルや知識を向上させることで、業務の質を向上し、業績アップに貢献できるような人材をつくることが目的です。
生産性の向上
人材が不足している状況において、限りあるリソースの中で最大限の成果を出すためには、生産性の向上が必要不可欠です。
人手が足りなくても、1人が3人分の働きをすれば、生産性が維持され、成果も向上します。
人材の流出防止
人材の流出防止は、目的であり目標でもある項目です。
コストをかけて採用した人材や優秀な人材の離職は、企業にとって大きな損失です。
人材育成で、のちの大きな戦力やリーダー候補になるような人材を育て、従業員の戦力化を図ることが重要となります。
リーダーシップの育成
企業を継続的に成長させていくためには、後継者の育成も重要です。
短期的ではなく、将来を見据えた中長期的な目線で人材育成に取り組みましょう。
企業が発展するためには、優れたリーダーが必要不可欠です。
そういった点で、中長期的かつ計画的な人材育成が求められます。
従業員のキャリア開発・自己実現
キャリア開発や自己実現のための人材育成を行えば、従業員のモチベーション向上につながります。
意欲のある従業員が増えれば、戦力となり、結果的に企業の成果に貢献します。
関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説
人材育成の方法

人材育成にはさまざまな方法があり、現場の負担や費用対効果などを考慮し、どんな手段で育成するかを決定します。
それぞれにメリットやデメリットがあるため、複数の方法を組み合わせて行うことも少なくありません。
近年新たに登場した育成方法も含めて7つ紹介します。
OFF-JT
OFF-JTは、現場以外で行う研修のことで、マネジメント研修やビジネスマナー研修などの集合研修やセミナーなど、座学がメインの育成方法です。
職場を離れて研修をするため、「職場外研修」と呼ばれることもあり、業務遂行のために必要な基礎知識や職能別の専門知識を学びます。
企業の担当者が講師をするケースもあれば、外部講師を招くこともあり、企業によって内容もさまざまです。
指導者のスキルによって左右されず、体系的に知識やノウハウを習得できる点がメリットです。
OJT
OJTは、座学がメインであるOFF-JTと違い、現場で実際の業務を通して教育を行う方法です。
現場の先輩や上司がトレーナーとして指導を行います。
実務を通してスキルやノウハウを身に着けるため、営業や接客、技術的な作業の指導に効果的です。
上司や先輩と教育を受ける人材がコミュニケーションを取れるというメリットがある反面、指導スキルによって効果に差が出てしまうというデメリットもあります。
関連記事:採用のミスマッチを防ぐリファレンスチェックとは?メリット・デメリットについて解説
eラーニング
eラーニングは、ネット上で研修を受けるもので、時間や場所にとらわれず実施することが可能で、移動コストがかからない点がメリットです。
オンデマンド配信だけでなく、WEB会議ツールなどを用いてリアルタイムに研修が受けられるものもあり、全国に拠点がある企業でも、従業員が一律で同じ研修を受けることができます。
自己啓発
自己啓発は、従業員自らの意思によって、自己のスキルを高めたり、知識を得たりするために学ぶことです。
福利厚生として資格取得支援制度や書籍購入補助が設けられているのは、自己啓発を促すためです。
企業には、自ら考えて行動できる主体性を持った人材が必要で、そのような人材を育てるには自己啓発が非常に有効です。
目標管理(MBO)
人材育成には、モチベーションを高めたり向上心を高めたりすることで人が育つという考え方もあります。
そこから生まれたのが目標管理=MBOです。
従業員それぞれが自分で目標を設定して自身で管理し、上司とコミュニケーションを取りながら目標の達成を目指します。
自己管理・評価を行うことで、内省の機会が得られ、目標達成のための工夫や改善に取り組めるようになり、自律的な育成につながります。
評価制度
目標管理と同じように、評価制度を設けることも人材育成につながります。
従業員それぞれの成果に対して、公正で適切な評価を行うことで、モチベーションを高め、主体性を養うことができます。
タレントマネジメント
タレントマネジメントは、個々の適性や潜在能力を引き出す手法です。
従業員の強みを引き出しながら、不足部分は研修によって補い、能力が最大限発揮できるように育成を行います。
関連記事:IPO準備企業が転職者を中途採用する際に気を付けるべきこと
人材育成のポイント

人材育成を成功させるためには、いくつか大切なポイントがあります。
6つのポイントを解説します。
目的を明確にする
人材育成は企業の成長・発展に貢献できるような人材を生み出すことです。
つまり、経営目標とリンクした目的を明確にしておくことが重要になります。
目的を明確にすることで、効率的な人材育成を行うことができるでしょう。
経営陣・部門担当者・人事が連携する
人材育成は、人事部だけが取り組むのではなく、企業全体で一体となって取り組むことが重要です。
経営目標と整合させるためには、経営陣と各部門が連携を取り、ビジョンを実現させるために人材育成の重要性や位置づけなど、共通認識を持つことが大切です。
階層別に適した方法を取る
新入社員、中堅社員、管理職など階層を分けて、それぞれに適した人材育成を行うことが大切です。
企業によって、各階層に求めるスキルレベルは異なります。
育成の指針となるよう、階層別に求める姿を定義しておくとよいでしょう。
関連記事:反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?
実践の機会とサポート体制を整備する
セミナーなどの座学で体系的に学んでいるだけでは、知識やスキルが定着しません。
インプットだけでなく、実践の機会を設けてアウトプットし、知識やスキルが自分のものとして身につくような育成を行うことが大切です。
また、学んだことが生かせる業務やプロジェクトに配置するなど、そのためのサポート体制を整備することが必要です。
指導側の育成も行う
指導する側のスキルや知識が十分でなかったり、指導方法が正しくなかったりすると、効果的な人材育成ができないだけでなく、早期離職の原因にもなってしまいます。
管理職や、OJT担当者に対しても研修を実施し、指導経験を積ませることを忘れないようにしましょう。
進捗・成果を可視化する
目標を達成するために、その進捗や成果を可視化できると、人材育成を効率的に行うことができます。
1on1や目標管理制度などで進捗を確認しながら、必要に応じて目標の追加や変更、施策の実施が大切です。
関連記事:従業員の反社チェックが必要な理由とは?チェックのタイミングと実施すべきサインも解説
まとめ
人材育成は、企業の成長や発展には欠かせない取り組みです。
人材育成を適切に行うことで、生産性の向上やリーダーシップの育成だけでなく、人材の流出防止にもつながります。
人材育成の方法はいくつかあるため、組み合わせて自社に合った育成を実施しましょう。
また、人材育成を成功させるには、目的を明確にし、企業全体が連携して取り組むことが大切です。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
関連記事:半グレと増加する闇バイト 新卒や若者にも必要な反社チェック