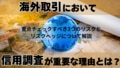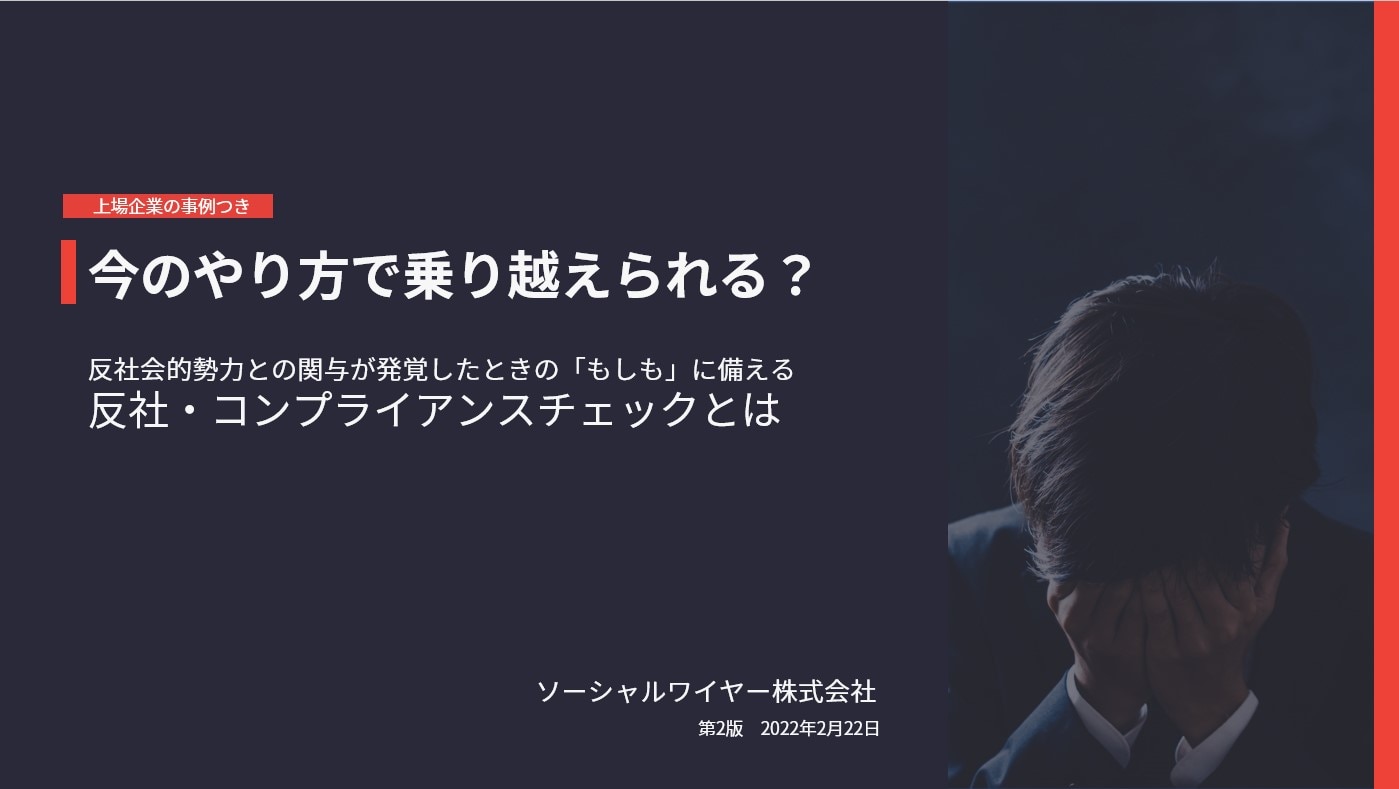知財戦略(知的財産戦略)とは?得られる効果と進め方、注意点ついてわかりやすく解説
グローバルな競争が激しくなっている現代において、高性能や高品質なサービス・製品を生み出すだけでは市場で勝ち抜くことができません。
実際、日本の圧倒的な技術によって作りだされた家電製品が、2000年代ごろから海外メーカーや異業種の参入により、競争力を失ってしまい、知財戦略について注目されるようになりました。
知的財産権は事業展開の大きな武器であり、経営に大きな影響を与えるものです。
この記事では、知財戦略によって得られる効果や、戦略の進め方、注意点についてわかりやすく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
注意すべき相手をすぐに発見できる反社リストを検索
目次[非表示]
- 1.知財戦略(知的財産戦略)とは
- 1.1.知財戦略の目的
- 1.2.経営戦略との関係
- 1.3.知的財産権と産業財産権の違いと種類
- 2.知財戦略による7つの効果
- 2.1.参入障壁の構築
- 2.2.侵害の排除
- 2.3.競合の動向把握
- 2.4.開発意欲の向上
- 2.5.ブランド・交渉力の強化
- 2.6.企業・投資価値の向上
- 2.7.ライセンス収益
- 3.知財戦略の進め方
- 3.1.経営環境の現状を分析する
- 3.2.知財戦略の策定
- 4.知財戦略の注意点
- 4.1.知財を保有するだけでは意味がない
- 4.2.出願しないという戦略もある
- 5.知的財産権を取るには
- 5.1.出願の流れ
- 5.2.主な知的財産権の費用
- 5.3.助成金の対象になることもある
- 6.まとめ
▶とりあえずダウンロード!【独自で収集した反社リストについてもっと知る】
知財戦略(知的財産戦略)とは

知的財産とは、創作的活動などによって生み出される、財産的な価値があるものであり、形を持たない無形資産のことです。
そういった知的財産を創造、保護、活用する戦略を、知財戦略と言います。
知財戦略の目的
知財戦略は、自社の知的財産を活用し、経営戦略に組み込むために重要なアプローチであり、市場を支配するための武器にもなります。
自社が開発した技術や製品を、特許など知的財産権として資産化し、その権利を行使することでほかの企業からの特許侵害などに対抗するのが主な目的です。
事業環境が常に変化する現代において、事業を成功に導き、企業価値を高めるために必要不可欠な取り組みです。
知財戦略を実行すると、以下のようなものが得られます。
- 市場優位性の確保
- ブランド価値の向上
- 収益の増大
- 投資やM&Aに対するアピール
- リスク管理
経営戦略との関係
企業が置かれた経営環境や経営戦略に応じて、最適な知財戦略は異なります。
最初に経営戦略があったうえで、その実現のためにどのように知財を効果的に活用するかという考え方であり、密接な関係にあります。
知財戦略は経営戦略の一部ですが、経営戦略の各戦略の方向性を決定するうえで重要な役割を果たします。
関連記事:IPO準備の前段階?自社の経営を上場基準に合わせる「ショートレビュー」とは
知的財産権と産業財産権の違いと種類
知的財産権と似た言葉で、「産業財産権」があります。
会社における産業財産権も、創造活動によって生み出された成果を保護する目的がありますが、知的財産権よりも狭い概念となっています。
また、産業財産権は経済産業省の特許庁が管轄ですが、知的財産権のなかには農林水産省へ出願するものもあります。
産業財産権の種類
産業財産権は知的財産権の一部であり、以下の4つの権利があります。
特許権 |
自然法則を利用した産業上利用可能な新しい発明を保護する権利です。 |
実用新案権 |
物の形状や構造、組み合わせに関する考案を保護する権利です。 |
意匠権 |
独創的で美観を持つ物品の形状や色、デザインなどを保護する権利です。 |
商標権 |
商品やサービスを区別するために使うマークを保護する権利です。 |
知的財産権の種類
知的財産権は、上記の産業財産権の4つの権利に加え、以下のようなものがあります。
著作権 |
文芸、美術、音楽、学術などの作品を創作した者が作品をどう使用するか決められる権利です。 |
回路配置権 |
半導体集積回路の回路配置について、創作者などに認められる権利です。 |
育成者権 |
新たな植物品種を育成した人に与えられる権利です。 |
地理的表示 |
地域の風土や製法で作られる農産品や、食品の伝統的な産地の名称を保護する権利です。(夕張メロンや神戸ビーフなど) |
商品表示・商品形態 |
表示や形態などに特徴のある商品を保護する権利です。 |
商号 |
営業上の会社名などを表す名称についての権利です。 |
関連記事:企業法務の役割と重要性とは?主な仕事や関連する法律について解説
知財戦略による7つの効果

知財戦略を適切に行うことで、企業が得られる7つの効果について解説します。
参入障壁の構築
知的財産権は、創作物を作り出した人に対して付与される「他人から無断で利用されない」権利です。
特許を登録し、それを業界他社に効果的にアピールすることで、競合の参入を大きく遅らせることができた事例が多数存在します。
侵害の排除
もし知的財産権がない場合、基本的には「自由競争」となり、参入してきた他者を排除することはできません。
権利を取得していれば、その権利を侵害された場合に、以下のような手段で対抗することができます。
- 警告状の送付
- 民事訴訟での差し止め・賠償金の請求
- 警察による没収・被疑者の検挙
- 税関での水際取締り
- ECサイトでの模倣品削除
模倣品を許容しないという姿勢を会社として打ち出すことで、自社のビジネスを守るだけでなく、侵害対策という意味で顧客との信頼関係も強化できるというメリットもあります。
関連記事:企業に欠かせないコンプライアンスオフィサーとは?主な業務・必要なスキルについて解説
競合の動向把握
知財戦略は、権利を取得することだけではありません。
特許・意匠・商標・実用新案などの産業財産権は、特許庁に登録することで権利が発生します。
この出願・登録された権利はデータベースで一般公開されているため、検索すると、競合他社がどのような技術を権利化しているのか、主要な発明者はだれか、その権利がいつまで有効なのかなどを把握することができます。
他社の技術動向を把握することで、自社ビジネスの方向性を決定することも、重要な知財戦略です。
開発意欲の向上
特許や意匠権などの知的財産権を取得するためには、コストが発生します。
費用は事務所によっても異なりますが、外部に依頼する場合、登録までに特許は1件あたり50~100万円、商標は1件あたり5~20万円程度が相場となっています。
これらの費用を「コスト」と捉えるだけでなく、開発意欲の向上に役立てることも知財戦略の1つです。
特許法35条のルールでは、職務発明を従業員が行った場合、あらかじめ契約などで取り決めておけば、使用者に「特許を受ける権利」を帰属させられる「職務発明」というルールがあります。
発明をした者には、その見返りとして相当の利益を与える必要があります。
「特許報奨金」や「全社員提案制度」などを設けることで、開発意欲を向上させ、知財を増やすことにつながります。
関連記事:人材マネジメントとは?その内容や必要性、ポイントを解説
ブランド・交渉力の強化
知的財産権を積極的に取得することで、他企業との交渉力を強化することができます。
例えば、他企業と共同開発をする際、すでに特許を取得したコア技術があり、開発の土台にできるとなれば、相手企業もタッグを組むメリットを感じられます。
また、ノンブランドのTシャツと有名ブランドのTシャツの価格が1桁異なるように、商標権で守られたブランドを確立することで、価格交渉力を高めることができます。
自社だけが自由に使える技術やブランドを保持しておくことは、他企業との差別化ができる要素となり、取引先やユーザーに指名される動機になります。
企業・投資価値の向上
企業が保有する知的財産について価値を評価して、投資やM&Aを実施する際の価格に反映する試みが以前から行われています。
特許庁からも、知的財産を定量評価するための算定方法が発表されており、知財の取得量や研究開発の成果を目に見える形で蓄積しているかどうかという点が、評価の対象となります。
また、直接的に数字換算せずとも、スタートアップ企業の将来性を評価する際に、技術力だけでなく知的財産権への取り組みも企業価値として評価する動きが強まっています。
ライセンス収益
知的財産権は、権利を保有することでブランドや技術を「独占」して他人の使用を禁止するだけでなく、他人に使用を「許諾」することができます。
特許を保有し、他社の知財の使用許諾することでライセンス収益を得るという知財活用の方法です。
自社で独占したい知財と、ライセンス収入や他社との交渉材料にしたい知財の違いを意識して権利化を進めることで、強い知財戦略を構築することが可能になります。
関連記事:スタートアップに求められるIPO準備で早く取り組むべき組織体制の整備とは
知財戦略の進め方

知財戦略の在り方は、企業の規模や業種、成長ステージによって異なります。
知財戦略を進めるためのステップとポイントを解説します。
経営環境の現状を分析する
自社が置かれている経営環境を把握し、知的財産による競争力強化の可能性を把握します。
まずは、事業内容や経営情報などから自社の現状分析を行います。
自社の弱み・強みなど現状を把握しましょう。
そして、自社が保有している知的財産について、相対的な評価を行います。
例えば、自社のサービスや製品、ノウハウに関する知的財産が、市場においてどのような立ち位置なのか、また競合他社がどのような知的財産を保有しているのか調査します。
知財ポートフォリオを活用することで、知財の相対価値や他社との差異が可視化され、自社の市場でのポジションを把握しやすくなります。
知財戦略の策定
自社の経営環境の現状を分析したら、そこから経営課題を明確にし、投資すべき重点分野を決定します。
経営資源には限りがあるため、自社の価値観や方針を踏まえた戦略を検討し、知財・無形資産が果たす機能や役割を明らかにしましょう。
関連記事:上場企業・IPO準備企業の陰に潜む反市場勢力とは?基本と用語について解説
知財戦略の注意点

知的財産権は、取得したうえで、適切に使いこなさなければ意味がありません。
知財戦略は、知的財産権を無駄にすることなく、かつ別のリスクを負うことなく進めなければいけません。
ここでは、知財戦略を有効に進めるための注意点を解説します。
知財を保有するだけでは意味がない
知的財産権を取得し、知財を保有するだけでは知財戦略とは言えません。
保有する権利をうまく活用し、収益を上げることが本来の目的です。
自社で使っていない知財がある場合、ライセンス契約を行ったり、売却したりするなど、収益化を図ることも必要となります。
出願しないという戦略もある
知的財産権を取得する際には、その内容を公開しなければいけません。
つまり、出願することで新技術の内容を他社に知られてしまうリスクがあります。
そのため、新技術を開発しても、競合に情報を与えないために、意図的に知的財産権を取得しない選択をすることもあります。
しかし、すべての技術に対して知的財産権を取得しないのはリスクとなるうえ、ライセンス収益を生み出すこともできません。
コア技術は権利を取得せず、それ以外の開発については権利取得してライセンス収益を得る方法も検討できます。
どの技術を出願するかという点も、戦略として考える必要があります。
関連記事:スタートアップに絶対押さえてほしい「IPO/M&A」を妨げる反社のワナ
知的財産権を取るには
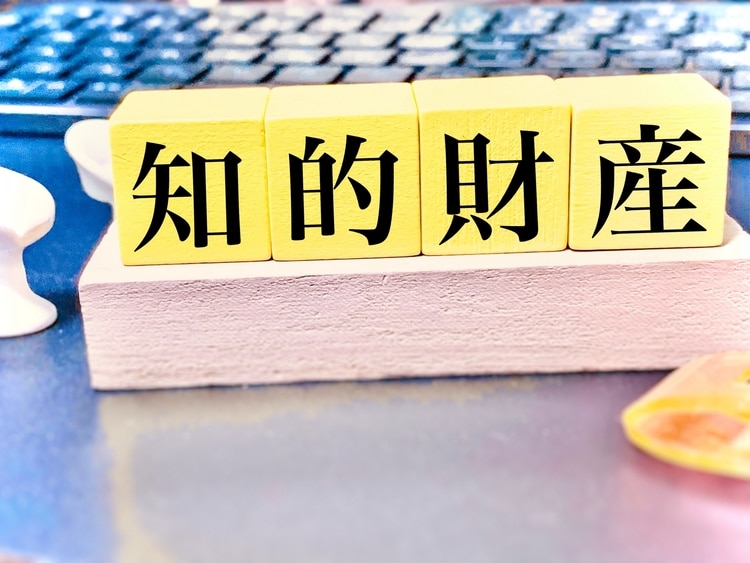
知的財産権を取得するための流れや費用について解説します。
出願の流れ
先行技術の調査を行い、出願可能と判断した技術について出願を行います。
特許など産業財産権は、それぞれの出願書類を外部サイトからダウンロードすることができます。
出願後、審査が実施され、審査に通ると権利を取得できるというのが一般的な流れです。
また、知的財産権を取得した場合、年間の登録料もかかります。
主に、3年ごとに支払いになるものが多いため、事前に調べておきましょう。
主な知的財産権の費用
主な知的財産権の出願にかかる費用は以下の通りです。
- 特許出願費用 14,000円
- 実用新案登録出願費用 14,000円(別途、実用新案登録料)
- 意匠登録出願費用 16,000円
- 商標登録出願費用 3,400円+区分数×8,600円
また、審査請求費用は以下の通りです。
- 特許出願審査請求費用 138,000円+(請求項の数×4,000円)
- 実用新案技術評価請求 42,000円+(請求項の数×1,000円)
実用新案については、出願時に実用新案登録料2,100円+(請求項の数×100円)が必要です。
関連記事:反社会的勢力に関する法律はある?各業界の対策と反社との取引を回避する方法も解説
助成金の対象になることもある
出願と審査請求は、助成金の対象となることがあります。
例えば、東京都江戸川区では、区内に本社を置く中小企業者に対して、以下の経費を助成する制度があります。
- 特許権の出願
- 実用新案権の出願
- 意匠権の出願
ほかにも、特許庁の特許料の減免制度などもあり、条件を満たした企業は対象になります。
国際出願に関する手数料の軽減措置などもあるため、必要な企業は申請を検討するとよいでしょう。
関連記事:コンプライアンスと企業倫理の関係とは?意識を向上させる取り組みについても解説
まとめ
知財戦略を有効に行うことで、自社の市場での優位性を確保し、企業価値や収益の向上につなげることができます。
また、設立したてのベンチャー企業や中小企業も、市場で優位に立ち、大企業とも対等に交渉が進められることにもつながります。
特許の出願をすることで、システムや技術の内容が知られてしまう可能性があるという注意点もありますが、長期的に考えると、知的財産権を取得することが安全策となることもあります。
どの技術を出願するのかという点にも配慮しつつ、知財戦略に取り組むことが大切です。
関連記事:コンプライアンスと法務の違いは?業務内容や部門を分けるメリット・デメリットを解説
関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説