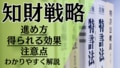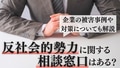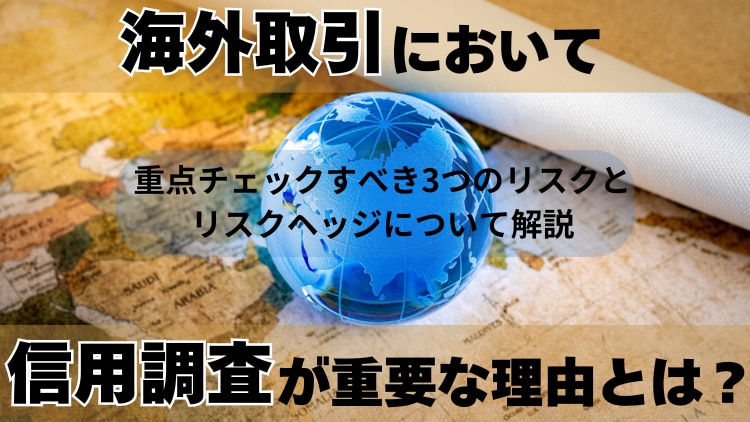
海外取引において信用調査が重要な理由とは?重点チェックすべき3つのリスクとリスクヘッジについて解説
海外取引における信用調査は、国内企業に対する調査と大きな違いはありません。
しかし、日本とは商習慣が異なるため、海外ならではの注意点が多数存在します。
グローバル化が進み、海外展開する企業が増加していますが、確実な債権回収のためには、信用調査は非常に重要です。
この記事では、海外取引において信用調査はなぜ重要なのか、また重点的にチェックすべきリスクや、リスクヘッジの方法についても解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
▼与信調査も行える!反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら
目次[非表示]
- 1.信用調査(与信調査)とは?
- 1.1.海外企業の信用調査が必要な場面
- 1.1.1.海外法人の設立
- 1.1.2.海外販売・ECサイト運営
- 1.1.3.海外事業展開と取引開始
- 2.海外取引において信用調査が重要な理由
- 2.1.主流の決済条件が掛売り
- 2.2.海外現地企業との直接取引の増加
- 2.3.直接会って話す機会が少ない
- 2.4.中国との貿易拡大で調査の需要が増加
- 3.国内取引と海外取引の違い
- 3.1.情報の透明性と取得難易度
- 3.2.法規制の違い
- 3.3.文化・言語の壁
- 3.4.その他の相違点
- 4.海外取引で重点チェックすべき3つのリスク
- 5.海外取引に利用できるリスクヘッジ
- 5.1.L/Cコンファメーション(L/C確認)
- 5.2.フォーフェイティング
- 5.3.海外(輸出)取引信用保険
- 5.4.日本貿易保険
- 6.まとめ
▶とりあえず使ってみる!【無料で与信調査もできる反社チェックツールを体験】
信用調査(与信調査)とは?

信用調査とは、企業の財務状況や経営状況、信用履歴などを分析し、取引をして良いかを判断するための調査のことで、与信調査や企業調査と呼ばれることもあります。
企業の買収や取引を開始する際、安全に取引ができるか、いくらまで取引して良いかを判断するために、契約前や契約更新のタイミングで調査を行うのが一般的です。
海外企業の信用調査が必要な場面
事業を海外に展開する際、信用調査が必要な場面は多数あります。
ここでは、特に代表的な3つのケースを解説します。
海外法人の設立
現地で法人を設立する場合、現地のパートナー企業や取引銀行とのパートナーシップ締結が必要になります。
その際、パートナー企業や金融機関が信頼できるのか、事前にしっかりと調査しておくことが大切です。
海外販売・ECサイト運営
海外に店舗を構えない場合でも、信用調査は必要になります。
ECサイトの運営や、現地代理店、サプライヤーと取引をする際にも、相手企業の財務状況や市場での信用度をしっかりと調査し、未払いリスクや不良在庫を避けるようにしましょう。
海外事業展開と取引開始
新たな市場に進出する際、取引先の情報をしっかりと把握し、予想外のリスクを低減させることが重要です。
海外進出の形は多様化していますが、どのような形であっても信用調査は行うようにしましょう。
契約不履行や未払いなどのトラブルを避けるだけでなく、現地企業との信頼関係の構築にも役立ちます。
関連記事:海外企業や外国人への反社チェックは必要?国際取引を安全に行う方法
海外取引において信用調査が重要な理由

信用調査は、国内の企業に対しても実施しますが、海外企業と取引を行う際は、特に調査の重要性が高まります。
その理由を4つ解説します。
主流の決済条件が掛売り
取引を行う際の決済として、先に製品・サービスを提供してあとから代金を回収する「掛売り」が主流になり、未収になるトラブルが多数発生したことが1つの理由です。
日本が経済大国として海外取引において中心となっていた時期は、日本企業に有利な条件下での決済方法でした。
しかし、グローバル化が進み国際競争が激化したことで、掛売りが主流になりました。
その結果、信用調査を行わないまま取引を行い、債権回収ができなくなるケースが多発しています。
特にアジア圏は政情なども不安定であり、一方的な取引の中止や、代金未払いのまま企業と連絡が取れなくなるトラブルが増加しました。
こういったことから、取引前の信用調査が必要不可欠となりました。
関連記事:BtoB企業が知っておくべき与信管理の重要性と効果的な方法
海外現地企業との直接取引の増加
以前の海外取引は、日系法人の海外支社や、現地法人化した工場などが、現地でビジネスを展開しており、日系の中小企業との取引が中心でした。
しかし、競争の激化によって、日系法人の市場シェアが低下し、海外の現地企業と直接取引を行うケースが増加しました。
前述のとおり、海外企業との取引は掛売りが主流となっているため、信用調査が重要となっています。
直接会って話す機会が少ない
海外ビジネスでは、国内のビジネスに比べ顔を合わせて直接商談することが少なくなります。
国内ビジネスでも、オンラインでの商談の機会は増加傾向にありますが、直接対面するよりも得られる情報は限られてしまいます。
数字やデータを確認することで、企業の信用度はある程度判断できますが、直接会って話すことで感じられる人柄や誠実さなども判断材料の1つです。
直接会って話す機会の少ない海外ビジネスにおいて、企業調査は非常に重要となります。
関連記事:海外取引先への契約書に暴力団排除条項を英語で盛り込むには 海外反社チェックも解説
中国との貿易拡大で調査の需要が増加
以前は中国の人件費が安く、日本企業が中国に工場を置き、製品を生産するオフショア生産が中心でしたが、近年は中国の国際競争力が高まり、互いに輸出入をするようになりました。
貿易する機会だけでなく、扱う金額も増加しており、取引に注意が必要になったため、信用調査が重要になっています。
中国企業は、他の海外企業よりも政治の影響を受けやすいという特徴があります。
過去には急な政府の方針変更によってビジネスが破綻した例も多数あります。
公開情報を確認するだけでは不十分で、現地の情勢を加味した信用調査を行うことを意識し、最低限の信用と安心を確認したうえで取引を行うことが重要です。
関連記事:与信調査とは?手続きや必要性、失敗しない方法を解説
国内取引と海外取引の違い

国内と海外では、取引におけるリスクや信用管理の方法など異なるポイントが多数あります。
国内取引と海外取引の違いについて解説します。
情報の透明性と取得難易度
国内では企業情報の開示が進んでいるため、商業登記情報や信用調査会社などから情報を簡単に得ることができます。
しかし、国によって情報開示のルールは違うため、情報の入手が難しいことも少なくありません。
海外企業の場合、専門の調査会社に調査を依頼する必要があるケースがほとんどです。
法規制の違い
当然のことですが、法制度は国によって異なります。
契約内容や債権回収の手続きについても、国ごとの法規制に対応が必要であるため、海外に詳しい専門家や現地のプロのサポートを利用するのが一般的です。
関連記事:IPO準備&急成長ベンチャーに必要な「契約管理」 法務体制強化でリスク管理
文化・言語の壁
国内では経営者同士の信頼や、対面した感覚でのリスク判断も可能ですが、海外の場合は文化や言語が違うため、意思疎通が容易ではありません。
取引におけるリスクを見落とす可能性があるため、注意が求められます。
その他の相違点
国内取引と海外取引のその他の相違点は以下のとおりです。
- 親会社が子会社の面倒を見ることが当然ではない
- 契約をスムーズに履行するかどうかは、関係性や業界での立場によって判断されることがある
- 代金を支払うのも当然でない
- 商慣習が異なるため、正しいことも違う
- 本社の人材も、現地に行けば現地の人とされる
- 国や宗教、民族によって判断の傾向にも違いがある
関連記事:企業コンプライアンス強化のために必要な「法人の本人確認」とは
海外取引で重点チェックすべき3つのリスク

海外企業との取引にはさまざまなリスクが存在します。
注意すべき点を3つ解説します。
倒産の可能性
最初に気を付けなければいけないのが、倒産の可能性です。
取引先の海外企業が倒産すると、債権の焦げ付きが発生し、自社に大きな影響を及ぼします。
取引先企業の倒産に注意が必要という点は日本企業との取引時も同様ですが、情報の入手が容易ではないことを理由に、十分な調査を怠らないようにしましょう。
支払いぶりの状況
海外では、期日通りに支払いを行うケースがかなり少ないという性質があります。
以下は、期日通りに支払いが行われている割合を国別に表にしたものです。
中国本土 |
台湾 |
香港 |
アメリカ |
カナダ |
56.3% |
77.2% |
26.3% |
59.5% |
33.8% |
ドイツ |
イギリス |
イタリア |
オーストラリア |
エジプト |
64.0% |
51.5% |
41.1% |
64.7% |
18.4% |
これはPayment Study 2024(CRIBIS D&B調べ)による調査結果ですが、50%を下回る国が複数存在します。
支払いが遅れれば、自社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
海外企業と取引をする際は、倒産の可能性だけでなく、支払いぶりについても考慮した判断が必要です。
関連記事:与信取引で発生するリスクとは?与信管理の方法とポイントも解説
事業停止の可能性
もう1つ注意が必要なのが、事業停止の可能性です。
倒産以外にも、事業停止、活動休止、操業不能など、企業が取引を継続できなくなるケースは多数あります。
中国を例に挙げて解説します。
2023年に倒産した企業数は、日本が8,690社、中国が7,121社と、中国の方が少なくなっています。
しかしこれは、法的倒産を行った企業数で、2023年に中国で法的な手続きを取らずに事業停止した企業数は約134万社あります。
つまり、倒産と違って焦付き債権は発生しませんが、販路の縮小や調達先の喪失などのリスクが発生する可能性があります。
倒産の可能性だけでなく、事業停止の可能性も考慮して信用調査を行う必要があります。
関連記事:後払いに欠かせない与信審査とは?審査のポイントと与信管理について解説
海外取引に利用できるリスクヘッジ

海外取引の場合、地域によってリスクヘッジの手段が異なります。
例えば、アメリカではファクタリング会社が売掛債権を買い取って代金を支払う、ファクタリングのシステムを利用することが多いです。
ファクタリング会社の場合、金利分を差し引いての支払いになるため、回収できるのは金利分を差し引いた金額になります。
ヨーロッパでは、主に保険会社が提供する取引信用保険が活用されています。
保険会社へ保険料を支払い、支払い遅延や取引先の倒産などによって回収できなかった金額に対する保険料を受け取るシステムです。
インドネシアやインドなどアジア圏では、国内L/Cが利用されることが多いです。
銀行を介した取引となるため、銀行引受手形というものがあり、銀行が取引先の代わりに支払いを行います。
これらのリスクヘッジの方法は、国自体の財政が不安定になった場合には成立しないケースもあります。
そういった場合には、日本の銀行や日本貿易保険などが提供している以下の方法でリスクヘッジを行います。
それぞれ詳しく解説します。
関連記事:与信リスクを回避するために必要な取り組みとは?与信管理のポイントも解説
L/Cコンファメーション(L/C確認)
L/C(Letter of Credit)とは、国際取引の際に利用される決済手段で、日本語では「信用状」と呼ばれます。
L/Cベースの取引を行っており、相手国の支払い停止や発行銀行が倒産した場合、日本の銀行が変わりに代金を支払ってくれます。
保証料は輸出者が負担しますが、L/Cの全額が保証されます。
フォーフェイティング
輸出企業が銀行に買い取ってもらった輸出手形が不払になっても、手形の買戻し義務を負わない形で、銀行が手形を買い取る貿易金融の手法です。
つまり、銀行に手形を買い取ってもらった時点で、回収が完了するということになります。
ただし、L/Cを発行した銀行に対して、日本の銀行がリスクを取れない場合は利用できないため、注意が必要です。
関連記事:企業のリスクマネジメントとは?リスクの種類や基本プロセス・手法をわかりやすく解説
海外(輸出)取引信用保険
海外の取引先が倒産したり、代金の不払いがあったりした際に、取引信用保険会社から保険料が支払われます。
倒産や債務不履行だけでなく、取引先国の為替取引制限や輸入制限、地震、戦争などに対するリスクも補償されます。
日本貿易保険
日本の企業が行う海外取引において、輸出不能や代金回収不能などが発生した場合のリスクを補償してくれる保険です。
利用するためには、輸出相手が日本貿易保険の海外商社名簿に記載されている必要があり、記載がない場合は信用調査報告書などを提出し、審査が必要となります。
関連記事:安全な取引を行うための与信管理規定とは?作り方とポイントも解説
まとめ
グローバル化が進み、海外との取引や海外進出など、海外展開を行っている企業も多いでしょう。
海外取引は、文化や習慣の違いから日本での当たり前が通用しないことも少なくありません。
取引におけるリスクを回避・低減するためには、取引先企業の信用調査が必要不可欠です。
また、取引先国の輸入制限や為替取引制限など、国内取引にはないリスクも存在するため、リスクヘッジをしておきましょう。
関連記事:日本版DBSとは?イギリスとの違いや採用における反社チェックについても解説
関連記事:契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)が必要な理由は?具体例と例文も紹介