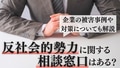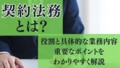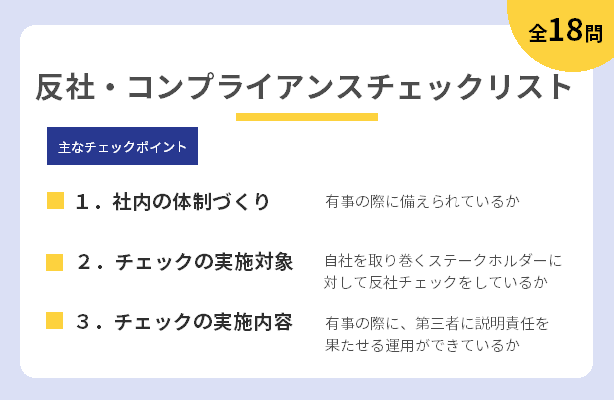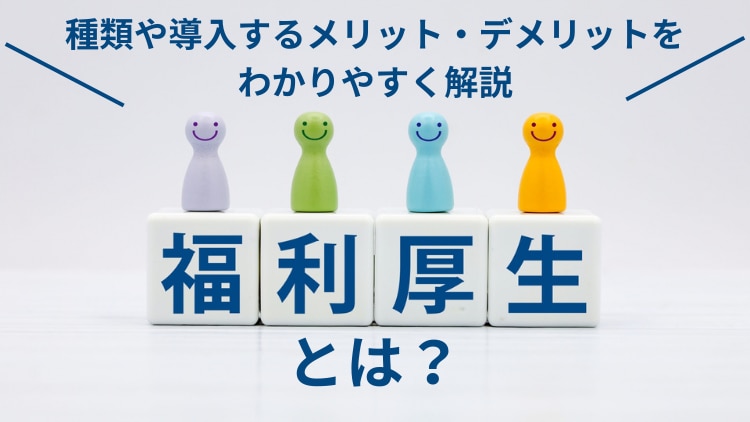
福利厚生とは?種類や導入するメリット・デメリットをわかりやすく解説
福利厚生は、従業員の満足度やモチベーションの向上だけでなく、健康経営や対外的な企業イメージの向上にもつながる、重要な人事施策の1つです。
この記事では、福利厚生の概要や種類、導入するメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
【参考】より深く知るための『オススメ』コラム
▼反社チェックツール「RISK EYES」の無料トライアルはこちら
目次[非表示]
- 1.福利厚生とは?
- 2.福利厚生の種類
- 2.1.「保険」に関する福利厚生
- 2.2.「手当」に関する福利厚生
- 2.3.「見舞金」に関する福利厚生
- 2.4.「休暇と休業」に関する福利厚生
- 2.5.「生活と仕事の両立支援」に関する福利厚生
- 2.6.その他のユニークな福利厚生
- 3.福利厚生を導入するメリット・デメリット
- 3.1.福利厚生を導入するメリット
- 3.1.1.採用の強化
- 3.1.2.従業員の満足度・モチベーションの向上
- 3.1.3.離職率の低下
- 3.1.4.優秀な人材の確保
- 3.1.5.節税効果
- 3.2.福利厚生を導入するデメリット
- 3.2.1.コストの増加
- 3.2.2.管理負担の増加
- 3.2.3.ニーズとのずれによる不満
- 4.福利厚生にかかる費用
- 5.福利厚生の運用形態
- 6.まとめ
福利厚生とは?

福利厚生とは、給与や賞与などの基本的な労働対価に加えて、企業が従業員とその家族に提供する報酬やサービスのことです。
働き方が多様化し、一昔前のように「終身雇用」となるケースはほとんどありません。
中途採用が当たり前になった現代において、優秀な人材を採用できるかどうかが非常に重要です。
また、人出不足が続いており、従業員が辞めない環境を作ることも大切です。
福利厚生を充実させることには、優秀な人材を確保し、安心して働ける環境を作ることで従業員離れを防ぐという目的があります。
企業での福利厚生の管理は、人事部や総務部が担当するのが一般的です。
関連記事:IPO準備企業が整備すべき人事・労務とは 懸念点についても解説
福利厚生の提供対象
福利厚生の提供対象は、以下の全ての労働者です。
- 正社員
- 正社員と同様の業務を行う有期雇用労働者
- 正社員と同様の業務を行うパートタイム従事者
- 派遣労働者
2020年4月に「改正パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止が明確にされました。
参考:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定例」
また、社会保険の適用範囲が拡大され、2024年10月以降、従来より多くの非正規労働者が社会保障制度の恩恵を受けられるようになりました。
福利厚生の法的種類
福利厚生には、法的な分類として「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つがあります。
いずれも、企業側が原則として負担し、「福利厚生費」として計上します。
それぞれ詳しく解説します。
法定福利厚生
法定福利厚生とは、法律で定められた福利厚生で、企業において導入・実施が義務付けられています。
保険や休暇に関する福利厚生のほか、労働安全衛生法などに基づいて実施が義務付けられている定期健診なども、法定福利厚生に含まれます。
法定外福利厚生
法定外福利厚生は法律で定められておらず、企業が任意で導入します。
内容も企業ごとに自由に取り決められますが、多くの企業で共通して導入されている福利厚生もいくつかあります。
住宅手当や通勤交通費支給、特別休暇の付与など、企業によってさまざまな福利厚生が導入されています。
関連記事:雇用に関連する法律と主なルール 違反した場合のリスクと罰則も解説
福利厚生の種類

福利厚生の種類について、より具体的に解説していきます。
「保険」に関する福利厚生
福利厚生における「保険」は、社員が働けなくなるなどの万一の事態や、産後や老後など将来のために備え、「安心して働けるようにする」という役割があります。
法定福利厚生の保険は、人材を雇用しており、一定の条件を満たした会社は加入する義務があります。
保険にかかる費用は、原則、会社と社員で費用負担するため、社員の給与から差し引くことが一般的で、会社負担分を法定福利費として計上します。
法定福利厚生の保険は以下の通りです。
名称 |
概要 |
健康保険 |
公的医療保険のひとつで、社員が病気やケガで働けなくなった場合に備え、社員本人とその扶養家族が加入します。大手企業は「健康保険組合」を設立、中小企業は「全国健康保険協会」を利用することが一般的です。 |
介護保険 |
介護が必要になった人を給付金で支える公的保険制度で、満40歳を超える社員は加入義務があります。 |
厚生年金保険 |
公的年金制度のひとつで、社員の老後や、働けなくなった時・死亡時に、社員と家族への救済が行えるように加入するものです。「特殊法人日本年金機構」が徴収業務を行います。 |
雇用保険 |
失業時や教育訓練の際、社員の生活を給付金で支える公的保険制度です。 |
労災保険 |
業務上または、通勤時に社員が病気やケガを負った際や死亡した際、社員とその家族へ補償が行えるように加入する公的保険制度です。 |
子供・子育て拠出金 |
育児支援や、仕事と育児の両立支援事業に充当される税金です。厚生年金と合わせて「特殊法人日本年金機構」が徴収業務を行います。 |
障害者雇用納付金 |
障がい者を雇用する事業主への支援に充てられる税金です。「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が徴収業務を行います。 |
法定福利厚生の保険をまとめて「社会保険」と表現されることがありますが、上記に挙げたどの保険をまとめて社会保険と呼んでいるのか、複数の定義があるため注意が必要です。
法定外福利厚生の保険があるのは、企業が任意で、民間の保険会社の提供する保険に加入しているケースです。
社員の死亡保障や休業補償、医療保障、企業年金などによる老後の保障があるほか、財産形成にあたる財形保険などがあります。
関連記事:雇用形態とは?保険の適用範囲や管理のポイントを解説
「手当」に関する福利厚生
手当とは、給与以外に支給される所得のことです。
各種手当を福利厚生の一部とすることがありますが、原則、手当は給与所得で、福利厚生の費用として計上することはできません。
手当も福利厚生と同様、提供義務が明記されているものと、会社の任意で提供するものがあります。
法令に定めのある主な手当は以下の通りです。
名称 |
概要 |
時間外手当・残業手当 |
社員が労働基準法を超えた(休憩時間を除いて1日8時間、週40時間まで)勤務を行った場合に支給します。 |
休日出勤手当 |
社員が休日にあたる日に出勤した場合に支給します。 |
深夜労働手当 |
深夜(22時~5時)に労働を行った場合に支給します。 |
出産手当 |
会社の健康保険に加入している女性社員が、出産のために給与の減額や支払いがない期間に支給します。 |
育児手当 |
雇用保険に加入する社員が育休を開始してから、子が原則1歳になるまでの養育に対して支給します。 |
傷病手当 |
会社の健康保険に加入する社員が、ケガや病気で働けない期間に支給します。 |
会社が任意で支給する主な手当は以下の通りです。
名称 |
概要 |
住宅手当 |
一定の条件を満たした社員に対して、家のローンや家賃の補助のため支給します。 |
通勤手当 |
勤務地までの通勤交通費を支給します。 |
テレワーク手当 |
オンライン勤務する社員に対して、通信費や諸経費などを補助するために支給するもので、「在宅勤務手当」とも呼ばれます。 |
役職手当 |
責任のある管理職の社員に支給されるもので、「職能手当」や「職務手当」とも呼ばれます。 |
食事手当 |
社員の就業時の食費を補填する目的で支給します。 |
家族手当 |
配偶者や子供など、被扶養者がいる社員に支給するもので、「扶養手当」とも呼ばれています。 |
出張手当 |
出張の際にかかる食事代などの諸経費を補助するために支給します。 |
研修手当 |
外部セミナーや研修、勉強会の費用を補助するために支給します。 |
資格手当 |
資格の取得をする際の費用や、褒章のために支給します。 |
関連記事:CFO(最高財務責任者)とは?役割と業務内容、CFO人材採用のポイントについて解説
「見舞金」に関する福利厚生
福利厚生の見舞金は、基本的には法定外福利厚生で、「慶弔見舞金」とも呼ばれています。
ただし、社会保険から一時金として支払われるものを「見舞金」と呼ぶことがあり、その場合は法定福利厚生となります。
法令に定めのある主な見舞金は以下の通りです。
名称 |
概要 |
出産育児一時金(出産祝い金) |
会社の健康保険に加入している女性社員に子供が生まれた際。支給される一時金です。配偶者が務める会社の健康保険に加入している場合は、「家族出産育児一時金」となります。 |
死亡一時金 |
厚生年金保険に加入している社員本人がなくなった際に、遺族へ支給される一時金です。 |
法令に定めのない主な見舞金は以下の通りです。
名称 |
概要 |
結婚祝い金 |
社員が結婚した際に支給される一時金です。 |
出産・就学祝い金 |
社員に子どもが生まれた際、子どもが就学した際に会社から支給される一時金です。 |
災害見舞金 |
社員が災害により被災した場合に支払われる一時金で、被害の程度によって金額が変動します。 |
傷病見舞金 |
社員が病気やケガをした際に支給される一時金です。 |
死亡弔慰金 |
社員が死亡した際に支払われる一時金で、死亡時が業務中か業務外かで金額が大きく変動します。また、会社の規模や社員の勤続年数などでも相場が変わります。 |
昇進祝い金 |
社員が昇進した際に支給される一時金です。 |
誕生祝い金 |
社員の誕生月に支給される一時金です。 |
関連記事:企業法務の役割と重要性とは?主な仕事や関連する法律について解説
「休暇と休業」に関する福利厚生
福利厚生の休暇は、法律で付与日数・基準が定められている「法定休暇」と、会社の判断で任意に付与される「特別休暇」があります。
法定福利厚生の主な休暇は以下の通りです。
名称 |
概要 |
年次有給休暇 |
年ごとに付与される法定の休暇です。継続勤務年数によって付与日数が変動します。 |
生理休暇 |
生理の日の社員に許可する休暇です。 |
介護休暇 |
要介護(2週間以上、常時介護が必要)と判断された家族がいる社員に対する休暇です。 |
子どもの看病休暇 |
小学校就学前の子どもを養育する社員に対し、子の看病が必要になった場合に取得を許可する休暇です。 |
法定外福利厚生の主な休暇は以下の通りです。
名称 |
概要 |
病気休暇 |
社員が病気になった際に利用できる特別休暇です。 |
忌引休暇 |
社員の家族の弔辞がある場合に付与される特別休暇です。 結婚などの冠婚葬祭をあわせて「慶弔休暇」と呼ばれることもあります。 |
結婚休暇 |
社員が結婚する際に付与される特別休暇で、社員本人だけでなく、社員の子の慶事にも適用される場合があります。 |
季節性の休暇 |
GWやお盆、夏季、年末年始など季節の連休に合わせて付与される特別休暇です。日程を会社で指定して全社的に休暇とするケースと、社員に日程を選択させるケースがあります。 |
リフレッシュ特別休暇 |
長期勤務している社員に対して、10年ごとなどの期間で付与される特別休暇で、「長期勤続休暇」とも呼ばれます。 |
ボランティア休暇 |
社員がボランティア活動を行う際に付与される特別休暇で、「社会貢献活動休暇」とも呼ばれます。 |
公務休暇 |
社員が公民権を行使する場合に付与される休暇で、裁判員に選ばれた際の「裁判員休暇」などがあります。 |
誕生日休暇 |
社員の誕生日に付与させる特別休暇です。 |
アニバーサリー休暇 |
社員の個人的な記念日に対して付与される特別休暇です。 |
教育休暇 |
社外の教育訓練や研修に参加する社員に付与する休暇です。 |
赴任休暇 |
引っ越しを伴う転勤や出向する社員に付与する休暇です。 |
関連記事:バックグラウンドチェックで休職歴は確認できる?発覚した場合の対応についても解説
法定外福利厚生の特別休暇は、就業規則内で定義されており、有給休暇となるか無給休暇となるかは会社ごとに定められています。
また、休暇と似た言葉で休業があります。
「働く予定である日の労働を免除する」という同じ意味ですが、法律などで厳密な定義はされていません。
一般的には、休暇は「1日単位で取得する」のに対し、休業は「週や月単位で取得する」という指針が見られます。
法定福利厚生の主な休業は以下の通りです。
名称 |
概要 |
産前産後休業 |
子を出産する前後で、女性社員に許可する休業です。 |
育児休業 |
社員の性別を問わず、子が1歳になるまで取得を許可する休業です。 |
法定外福利厚生の主な休業は以下の通りです。
名称 |
概要 |
病気休業 |
社員が病気やケガで仕事を行えない際に利用できる休業です。 |
ボランティア休業 |
社員が長期でボランティア活動を行うため、仕事ができない際に利用できる休業制度です。 |
留学休業 |
社員が海外留学によって仕事ができない場合に許可される休業制度です。 |
不妊治療休職 |
社員が不妊治療に専念するために利用できる休職制度です。 |
また、「ベビーシッター派遣制度」や「家事代行サービスの費用補助」、「託児所設置」など育児をする社員に対して手厚くサポートする企業もあります。
関連記事:コンプライアンスの意味と使い方 維持・推進する方法も紹介
「生活と仕事の両立支援」に関する福利厚生
「生活と仕事の両立支援」は、社員の働きやすさを実現するためのもので、国が提唱する「働き方改革」でも推奨されています。
該当する主な福利厚生は以下の通りです。
ジャンル |
具体例 |
働き方関連 |
|
キャリアアップ支援 |
|
お金関連 |
|
上記のものは全て法定外福利厚生ですが、「生活と仕事の両立支援」は今後も需要が高まっていくと言われています。
福利厚生で他社との差別化を図るには、この分野の福利厚生を検討するとよいでしょう。
関連記事:IPO準備企業が上場審査に向けて整えるべき労務管理体制とは
その他のユニークな福利厚生
法定外福利厚生は、企業独自で導入ができるため、ユニークな施策として有名な事例がいくつかあります。
有名なものは以下の3つです。
- さいころで手当の金額が決まる
- カイロプラクティックやネイルケアの実施
- 15万円の旅行代金プレゼント
このような福利厚生の導入は、「面白いことをやっている会社」という印象を与えるだけでなく、企業の独自性や文化を表現する1つの手段にもなっています。
関連記事:経営戦略とは?目的と段階を解説 知っておくべきキーワードも紹介
福利厚生を導入するメリット・デメリット

福利厚生を導入するメリット・デメリットをそれぞれ解説します。
福利厚生を導入するメリット
福利厚生を導入することで、企業が得られるメリットを5つ解説します。
採用の強化
福利厚生を充実させることで、働きやすい環境を整え、待遇を向上させることで採用力を強化することができます。
従業員の満足度・モチベーションの向上
福利厚生が充実すると、残業時間の削減やフレックス制度の導入、休暇の付与などにより、ワークライフバンスが整えられます。
プライベートな時間も充実させられることで、従業員の満足度が高まります。
また福利厚生には、労働環境を整えるサービスなども含まれています。
従業員が働きやすいと感じることで意欲が向上し、一人ひとりの能力を活かすことにつながります。
離職率の低下
働きやすさやプライベートの充実につながる各種福利厚生が充実すれば、従業員が健康に暮らしながら安定した生活を営めるほか、この会社で働き続けたいという気持ちが高まるでしょう。
優秀な人材の確保
企業に勤める従業員のうち、若い世代ほど会社の福利厚生を重視して勤務先を選んでいる傾向があるという調査結果があります。
参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」
また、IT人材を対象とした民間企業によるwebアンケートによると、「福利厚生を重視する」と回答した人は全体の6割を超え、20代では8割を超えています。
福利厚生の充実は、求職者のニーズに応え、優秀な人材を確保するために欠かせない要素と言えます。
節税効果
福利厚生にかかる費用は、一定の条件を満たせば福利厚生費として経費計上することができ、法人税の節税につながります。
関連記事:半グレと増加する闇バイト 新卒や若者にも必要な反社チェック
福利厚生を導入するデメリット
福利厚生を導入するデメリットを3つ解説します。
コストの増加
福利厚生を導入することで節税につながるというメリットがある反面、経費計上できないさまざまなコストがかかるというデメリットがあります。
企業負担分の福利厚生費用だけでなく、福利厚生の運用や管理などにも人的コストが発生することを念頭に置いておきましょう。
管理負担の増加
福利厚生は、制度によって処理方法が異なっていり、必要な書類の作成や利用サービス窓口とのやり取りなど、事務作業が多数発生します。
福利厚生を増やせば、管理する負担も増加します。
従業員の利用率を調査し、利用率の低い制度は廃止することを検討するとよいでしょう。
ニーズとのずれによる不満
どのような福利厚生を導入するかどうかは、企業側のビジョンや目的だけでなく、 従業員の価値観や年齢、ライフスタイルによっても異なります。
せっかく導入しても従業員のニーズに合っていなければ、利用頻度が低かったり、不満の原因になったりすることがあります。
すべての従業員が満足する福利厚生は存在しないということを前提として、時代や社会上状況の変化に合わせて、定期的な見直しが必要です。
関連記事:人材管理の方法は?手順やメリット、データベースの作成方法を解説
福利厚生にかかる費用
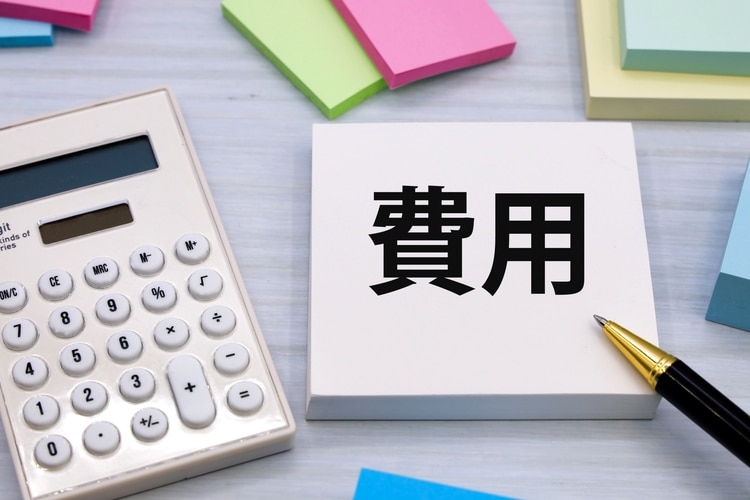
福利厚生にかかる費用について、日本経済団体連合会が実施した福利厚生費に関する調査があります。
この調査によると、企業は従業員1人当たり、月10万8,517円負担しています。
このうち、法定福利厚生は8万4,392円、法定外福利厚生は2万4,125万円となっています。
項目別に見ると、以下のようになっています。
法定福利厚生 |
従業員一人当たりの金額/月 |
健康保険・介護保険 |
3万1,041円 |
厚生年金保険 |
4万6,832円 |
雇用保険・労災保険 |
4,810円 |
子ども・子育て拠出金 |
1,671円 |
その他 |
39円 |
参考:日本経済団体連合会「2019年度福利厚生費調査結果の概要」
関連記事:バックグラウンドチェックの費用相場は?調査会社の選定基準も解説
福利厚生の運用形態
福利厚生の運用は、大きく分けて自社運営型、アウトソーシング型、ハイブリッド型の3つの方法があります。
企業規模や業種、コストや従業員のニーズを考慮して、適切な形態を選択することが重要です。
それぞれの方法について解説します。
自社運営型
自社運営型は、企業が自ら福利厚生のサービスを企画・運営し、従業員に提供する方法です。
企業の特性や細かなニーズに合わせて提供することができますが、運営コストや人的負担が大きいのが課題です。
アウトソーシング型
アウトソーシング型は、福利厚生サービスの運営を外部の業者に委託する方法です。
- パッケージプラン(定額制)
- カフェテリアプラン(ポイント制の選択型)
主に上記2つの方式があり、近年多くの企業で利用されています。
専門業者のノウハウを活用することが可能で、運営コストや人的負担を削減できるメリットがあります。
一方、中小企業の場合はポイント制を選択すると割高になったり、自社の特性を反映しづらかったりする点がデメリットです。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、自社運営型とアウトソーシング型を組み合わせる方法です。
基本的なサービスはアウトソーシングしながら、特殊なサービスなどは自社で運営するなど柔軟に運用できることがメリットです。
しかし、管理が複雑になるという課題があります。
関連記事:反社チェックを自動化する方法はある?ツールの機能や注意点を解説
まとめ
この記事では、福利厚生の種類やコスト、運用形態について解説してきました。
福利厚生を導入することで、コストや管理などの負担は発生しますが、従業員の満足度を上げ、優秀な人材を集めることができるなどさまざまなメリットがあります。
また、運用形態もいくつかあるため、自社にあったサービス内容、運用を選択しましょう。
関連記事:バックグラウンドチェックは何年前まで調査が必要?前職調査で聞くべき内容も解説
関連記事:採用時に反社チェックが欠かせない理由とは?企業側のリスクと注意点も解説